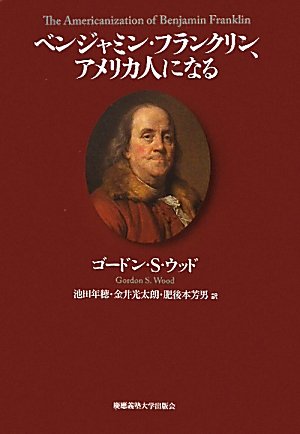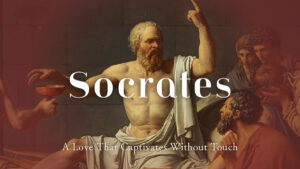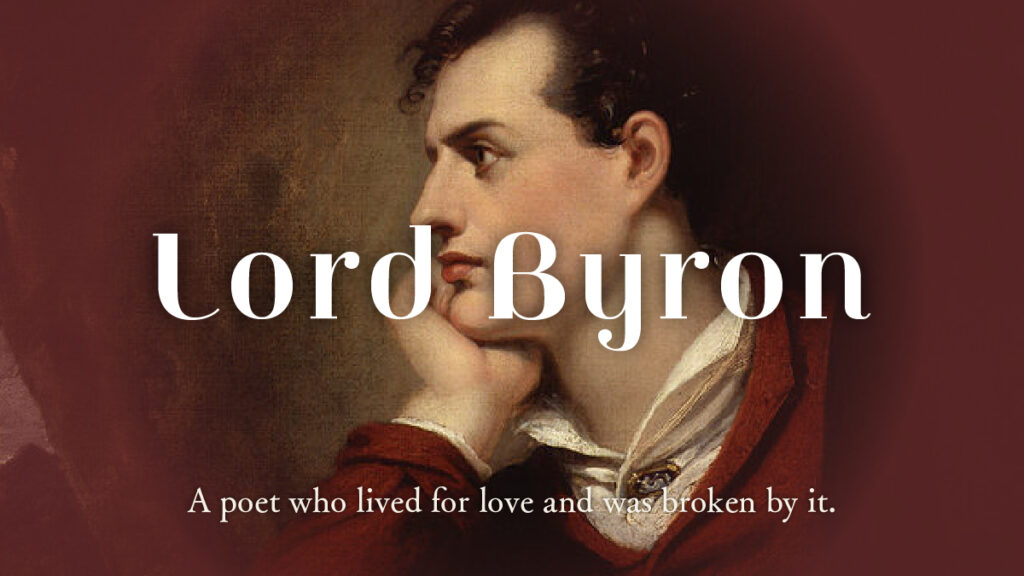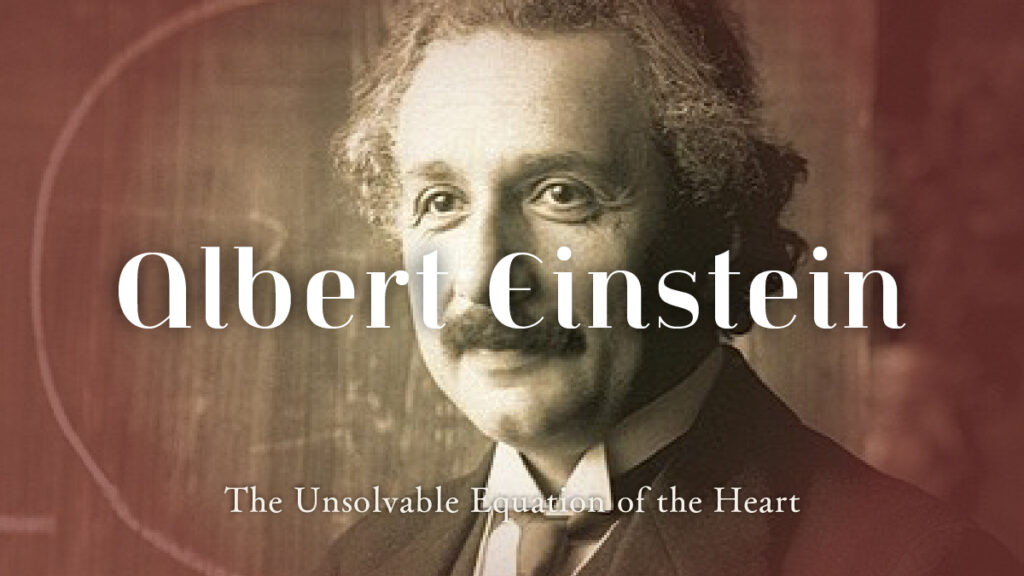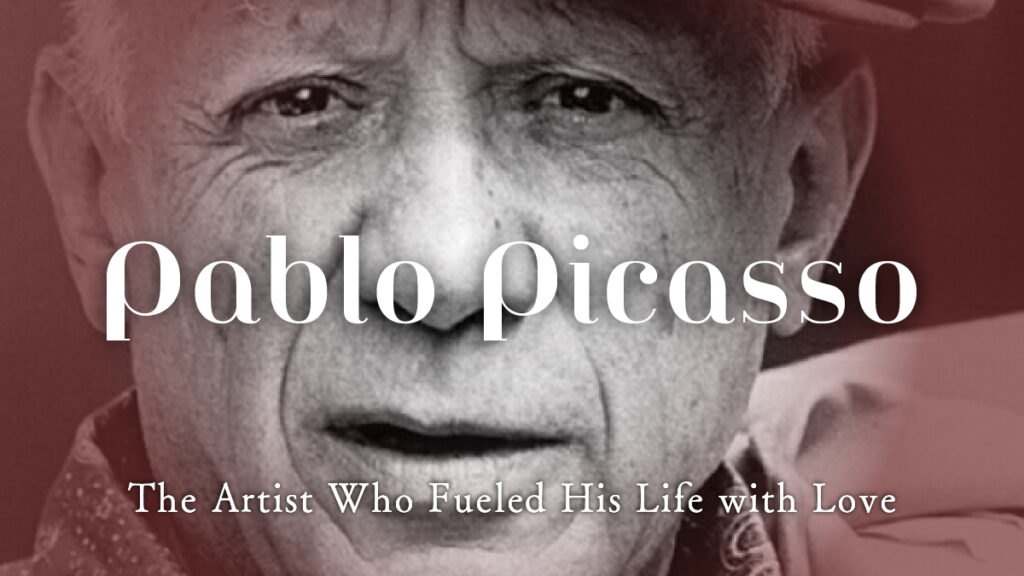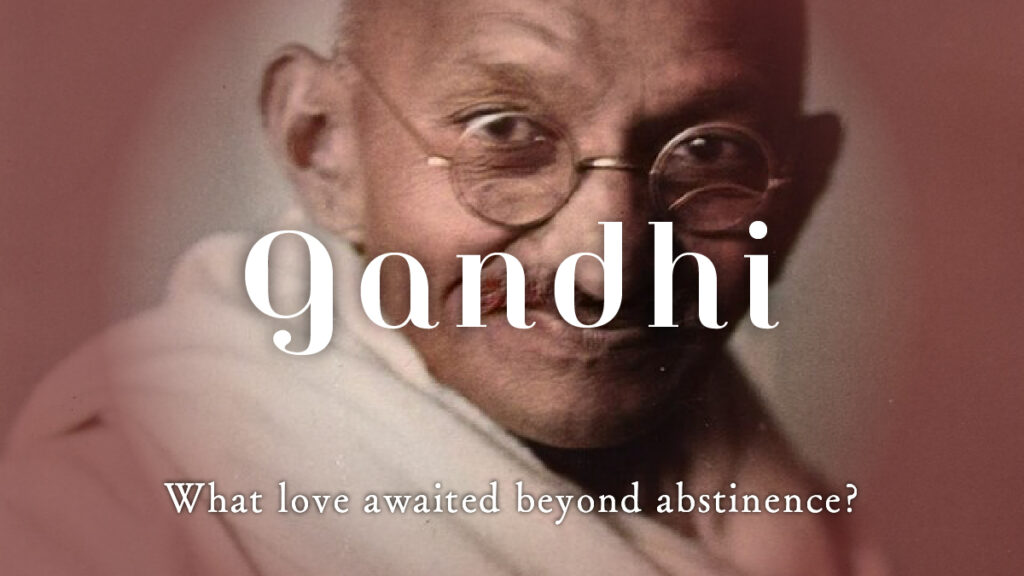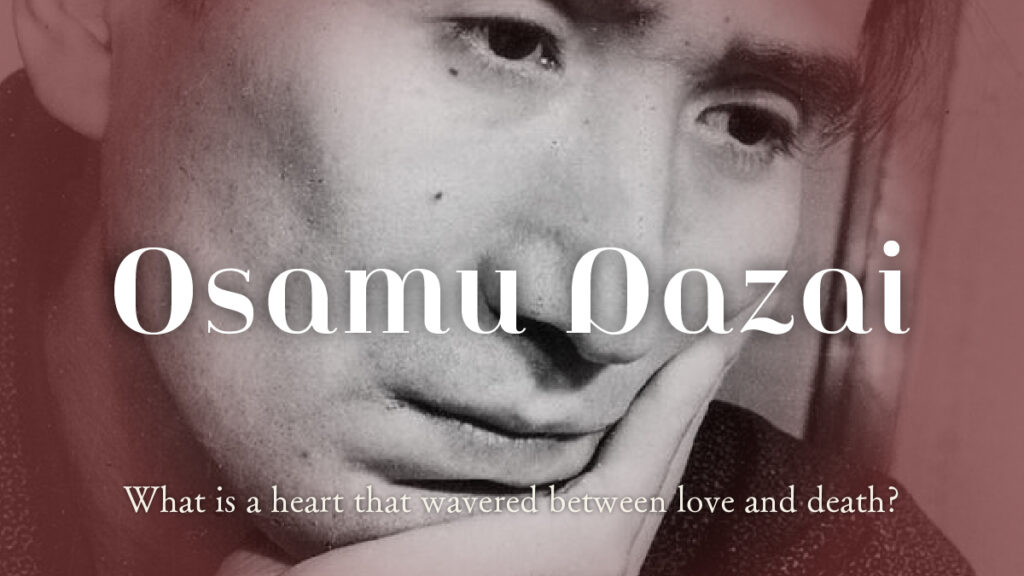ベンジャミン・フランクリンの恋愛観に迫る|“雷の発明家”が落ちた恋とは?
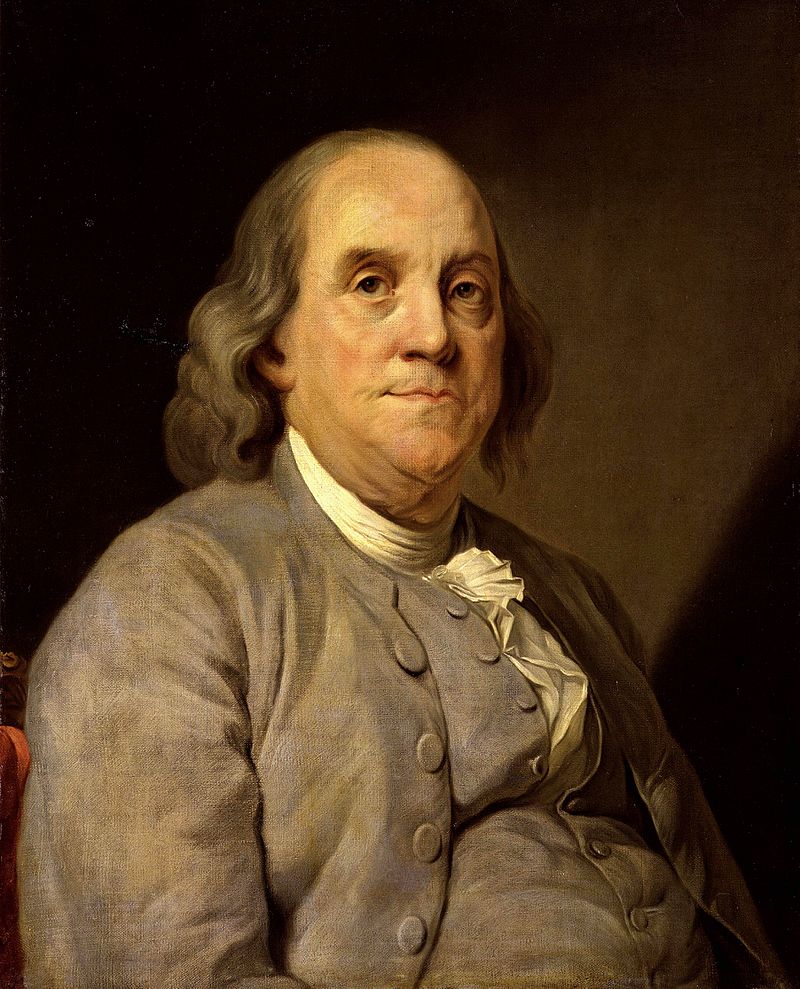
ベンジャミン・フランクリン。
1706年、ボストンのロウソク職人の家に生まれ、17人兄弟の15番目として、にぎやかな光の中で育った。
政治家としてはアメリカ独立宣言の起草者のひとり、科学者としては雷の正体を暴いた実験で知られる。
外交官、発明家、作家としても才を発揮した、まさに“知と行動”の巨人だった。
だが、その輝きの裏には、雷よりも予測できぬ恋の情熱が潜んでいた。
本記事では、そんなベンジャミン・フランクリンの“恋愛の歴史”に焦点を当て、知と情熱を併せ持った男の心の軌跡をたどっていく。
青年以前の恋と光

はじめての「それらしき」気持ち
ベンジャミンがまだ10歳にも満たなかったころ。
教会で出会った近所の年上の少女に、密かに憧れを抱いていたという話が残っている。
日曜礼拝の帰り道、彼女が落とした祈祷書を拾って渡した時、彼女がにっこり笑った——というような、初恋めいた空想は、後世の誰かが書き加えたのかもしれない。
だが、彼が生涯にわたって、女性に対して知的な親和性と観察眼を向けていたことを考えれば、
その“最初のまなざし”が、このころ芽生えていたとしても不思議ではない。
印刷所の裏で芽生えたもの
10代のフランクリンは兄の印刷所で働きながら、文字と思想に夢中になっていた。
鉛の匂いとインクのにおいが混じる作業場の片隅で、
時折ふとした瞬間に見せる年上の女性たちへの眼差し。
だが、ただの少年の片思いとは違った。
彼は、彼女たちの表情や言葉、衣擦れの音までを観察し、
まるで科学者が雷雲を見つめるように、恋を「知ろう」としていた。
若くして家出し、フィラデルフィアへと渡った彼は、
いくつかの淡い恋に出会うが、いずれも一時の通過点でしかなかった。
ロンドンと孤独と欲望と
17歳でロンドンへ渡ったとき、彼はすでに「書き手」としての自意識を持っていた。
印刷業で糊口をしのぎながら、書簡や随筆を書き連ね、時折出会う女性たちと束の間の会話を楽しんだ。
けれど、ロンドンの冬は厳しく、安宿の冷たい毛布は、
精神を癒すにはあまりに頼りなかった。
彼は、女性との一夜に温もりと救済を求めるが、そこには満たされなさも残る。
ロンドン滞在中、彼は「ミス・ウィリアムズ(Miss T)」という女性と短いが濃い関係を持ったとう噂がある。
同じ宿に住んでいた若い彼女に対して、情が移り、ある種の恋心と欲望が混ざった経験をしたようだ。
彼は後年、「若さゆえの過ち」として、どこか懐かしむような調子で自伝ににじませている。
この頃から彼の中で、「理想の恋愛」と「現実の情事」の間に、
はっきりとした距離が生まれはじめていたのかもしれない。
秋風に吹かれて、結婚へ

妻デボラとの、かたちのない契約
1723年、17歳のベンがフィラデルフィアに移り住んだ直後、彼はある若い女性に出会う。
彼女の名はデボラ・リード。ベンより2歳年下だった。
ベンは彼女に恋をし、求婚までしたが、
デボラの母親がこの若き印刷工の将来に不安を抱き、すぐの結婚は許されなかった。
その後ベンはロンドンへと旅立ち、デボラは別の男──ジョン・ロジャーズ──と結婚する。
ところがこのロジャーズ、すぐに行方をくらまし、しかも重婚の疑いがある問題人物だった。
当時の法律では、夫の生死が不明である限り再婚は禁じられていた。
そのため、デボラは正式な再婚ができない立場となり、
社会的にも中途半端な境遇に置かれることになる。
それでもベンはロンドンから帰国後、彼女と「法的でない同棲関係」を選び、
事実婚という形で家庭を築いたのだった。
フランクリンには、事実婚を始める前にすでにもうけていた婚外子ウィリアムがいた。
母親の素性は不明だが、1730年頃に生まれたとされ、ベンと共に暮らし始めた。
その後、デボラとの間に実子フランシスとサラが誕生し、三人の子どもを共に育てていくことになる。
ベンは日記に淡々と子の誕生を記録し、派手な愛情表現こそなかったが、
そこには静かな敬意と責任感、そして確かな家庭の温もりが流れていた。
晩年の恋と、静かな別れ
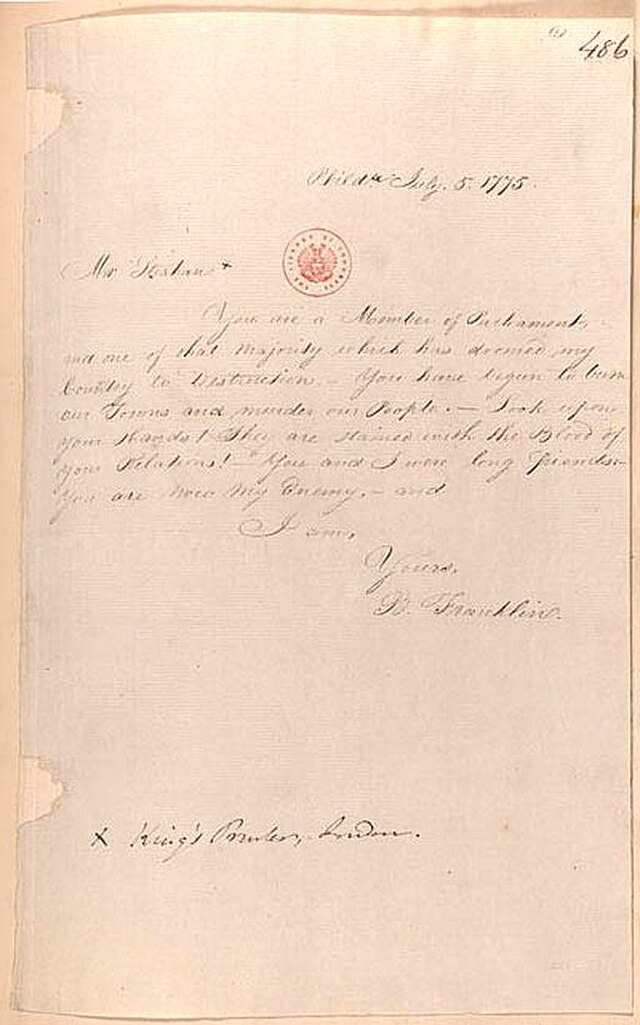
パリの貴婦人と恋文と
50代後半を迎える頃、フランクリンとデボラのあいだには、目には見えない距離が静かに生まれはじめていた。
病弱なデボラはフィラデルフィアに留まり、家庭を守っていたが、夫婦の会話は次第に減り、手紙のやりとりも減少していった。
気がつけば、互いの心が手の届かない場所にあるような感覚だけが残っていた。
それでも、ベンは「愛すること」をやめる人間ではなかった。
70歳を超えたベンは、アメリカ独立の外交交渉のためパリに渡る。
政治家としての使命を背負いながらも、彼の周囲には不思議と女性たちの温もりが絶えなかった。
その中でもとりわけ印象的な存在だったのが、
音楽好きの才媛マダム・ブリヨンだった。
ブリヨン夫人とは頻繁に手紙を交わし、
ベンは「あなたの騎士」と名乗り、彼女はそれを「小さな冒険」と呼んだ。
そのやりとりは恋文にして遊戯。
熱はあっても火傷はしない、そんな言葉のダンスだった。
未亡人へのプロポーズと、年上の哲学
時が経ち、ベンはマダム・フィシェという哲学者に、より深い情を抱くようになる。
フィシェ夫人との関係は、ブリヨンとの軽やかなやり取りとは一線を画していた。
彼女は思想家ヘルヴェティウスの未亡人であり、その晩年を哲学と芸術に囲まれたサロンで過ごしていた。
そこに通う人々のなかで、ベンは一際熱心な来訪者だった。
フィシェに対して、彼は真剣な恋心を抱き、ついには結婚を申し込んだ。
だが彼女は、亡き夫への忠誠を理由にそれを断った。
それでもベンは諦めなかった。
彼は何通も何通も、まるで若者のように情熱的な手紙を送り続けたのだ。
ふたりの関係は、肉体を超えた場所で深く結ばれていたと言っていいだろう。
だが、そのやりとりの中には、老境に差しかかってなお揺らめく、ひとつの真剣な「愛」の形があった。
相手の思想に敬意を払いながらも、感情を込めて言葉を投げかける。
それは、年齢も立場も超えた、魂と魂の対話だった。
年上女性を愛した理由
ベンは、年上の女性たちに対してどこか抗えない魅力を感じていた。
彼はかつて、匿名文として「年上の女性をすすめる八つの理由」という随筆を発表している。
そこで彼は、年上の女性は理性的で感情のコントロールができること、話が合いやすいこと、秘密を守ることに長けていること──
そして何より、彼女たちとの時間は「より精神的で、心が満たされるものだ」と書いた。
軽い風刺と見せかけながらも、そこには彼自身の恋愛哲学がにじんでいる。
若さの燃焼よりも、静かな対話。
熱情よりも、知恵と包容。
それが、ベンが恋に求めた「質」だったのかもしれない。
死を目前にして

その手紙は、永遠に
晩年のベンは、フィラデルフィアの自宅で静かに暮らした。
妻デボラは66歳でこの世を去ったが、二人は四十年以上も事実婚を続けた。
その後は、書斎と手紙に囲まれながら、穏やかなひとりの時間を生きた。
書斎の窓辺には、過去に交わした手紙が積み上げられていた。
それらはすべて、愛する人たち──家族や友人、
そして幾人かの女性たち──への応答であり、問いかけだった。
死の床につく前、彼は子供たちに向けていくつかの手紙を残したとされるが、内容の多くは失われている。
彼は最後まで、人を想い、人をクスッと笑わせるようなひと言を、どこかに忍ばせた手紙を遺したのかもしれない。
ベンジャミン・フランクリンの恋愛観とは?
彼の恋愛観は、生涯を通して変化し続けた。
若き日は情熱と好奇心に、壮年期は責任と選択に、
そして晩年は、対話と尊重、そして静かな憧れに彩られていた。
恋は、若者の特権ではない。
そう、ベンは静かに証明してみせた。
愛は、数式のように定義できず、雷のように予測もつかない。
だが、そこに確かに「温もり」があることだけは、彼は知っていた。
彼は人生のなかで、数々の女性に出会い、愛し、別れ、そして手紙を書いた。
それはただの感情の記録ではない。
電気と同じように、目に見えず、しかし確かに人を動かす力だった。
あなたの心のどこかにも、
誰かの心をそっとあたためる、
明るい光がひそんでいるのではないだろうか?
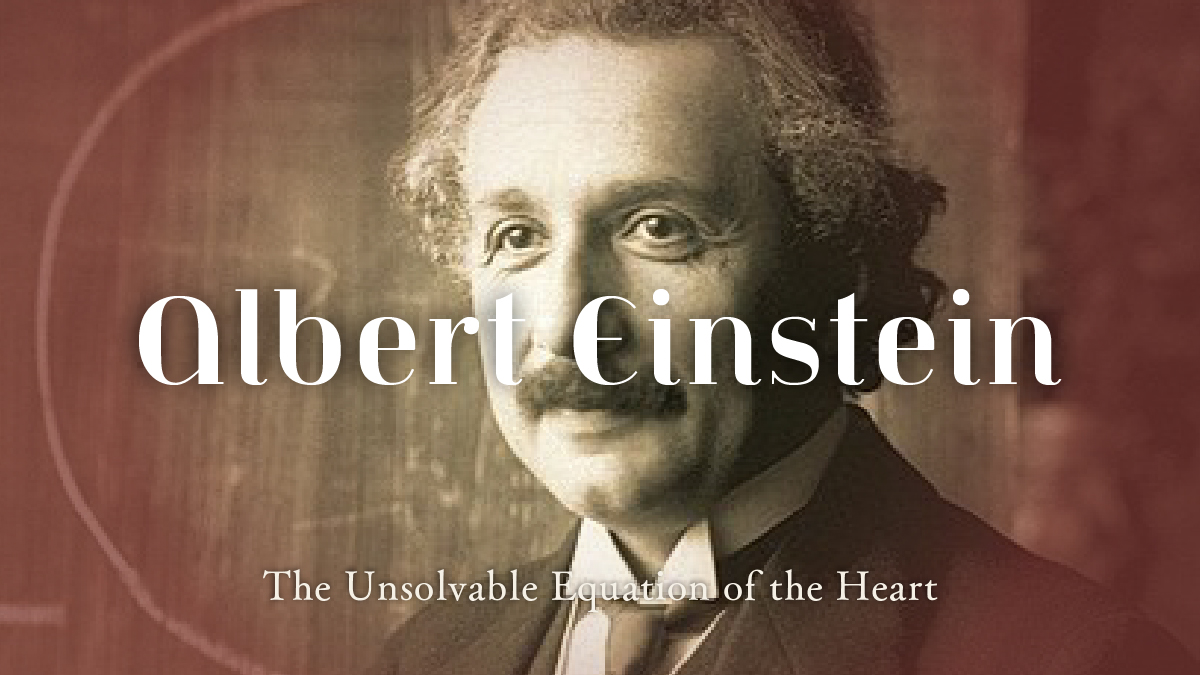



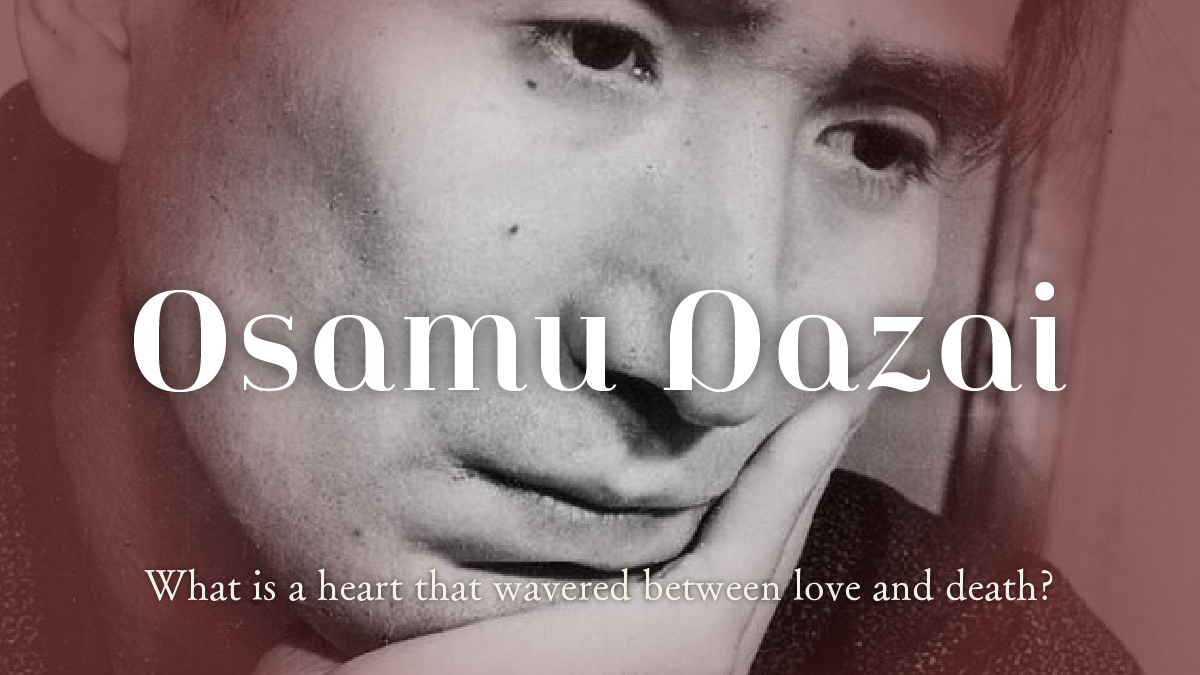
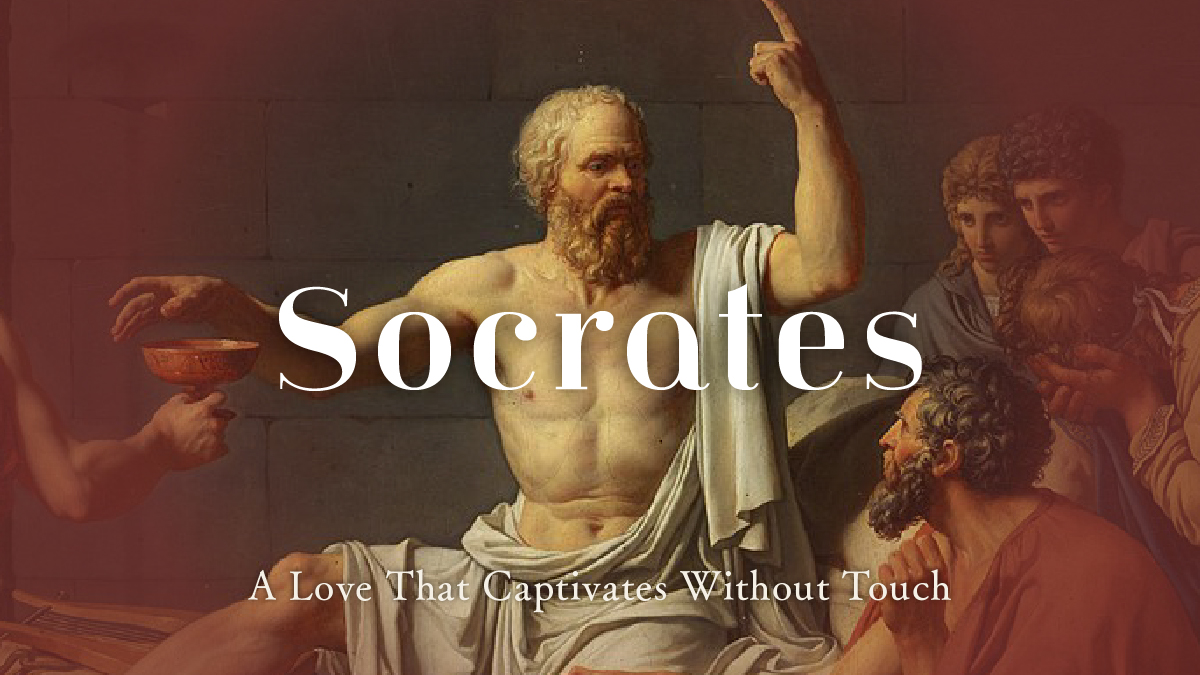

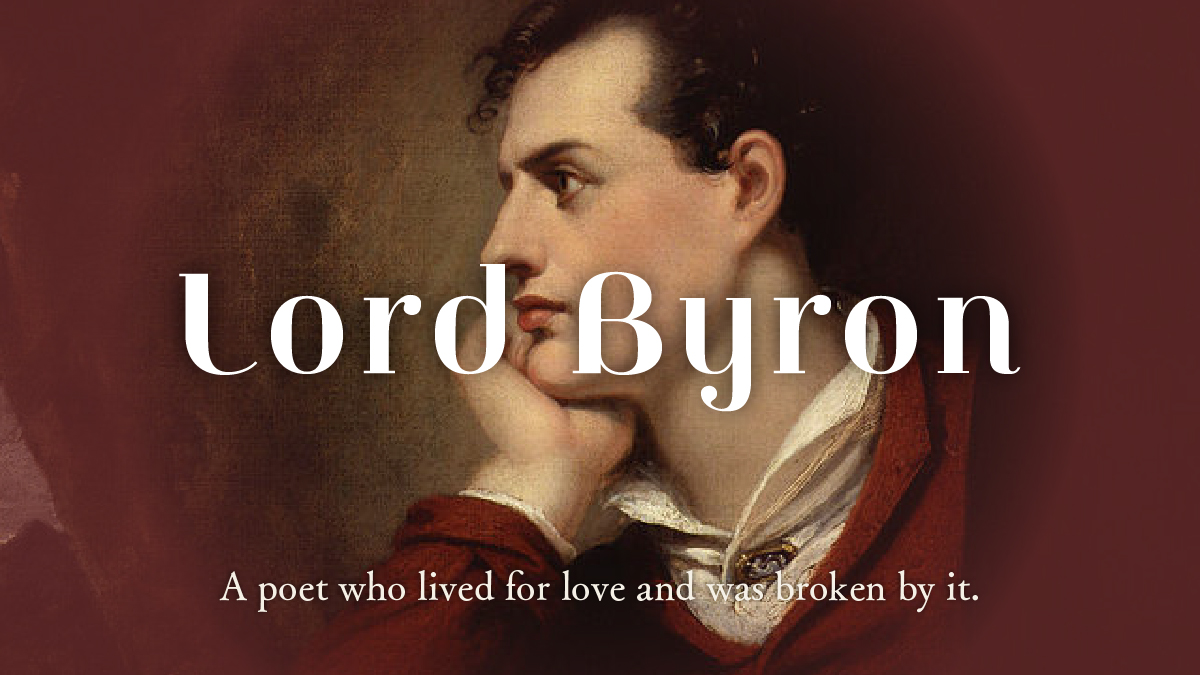





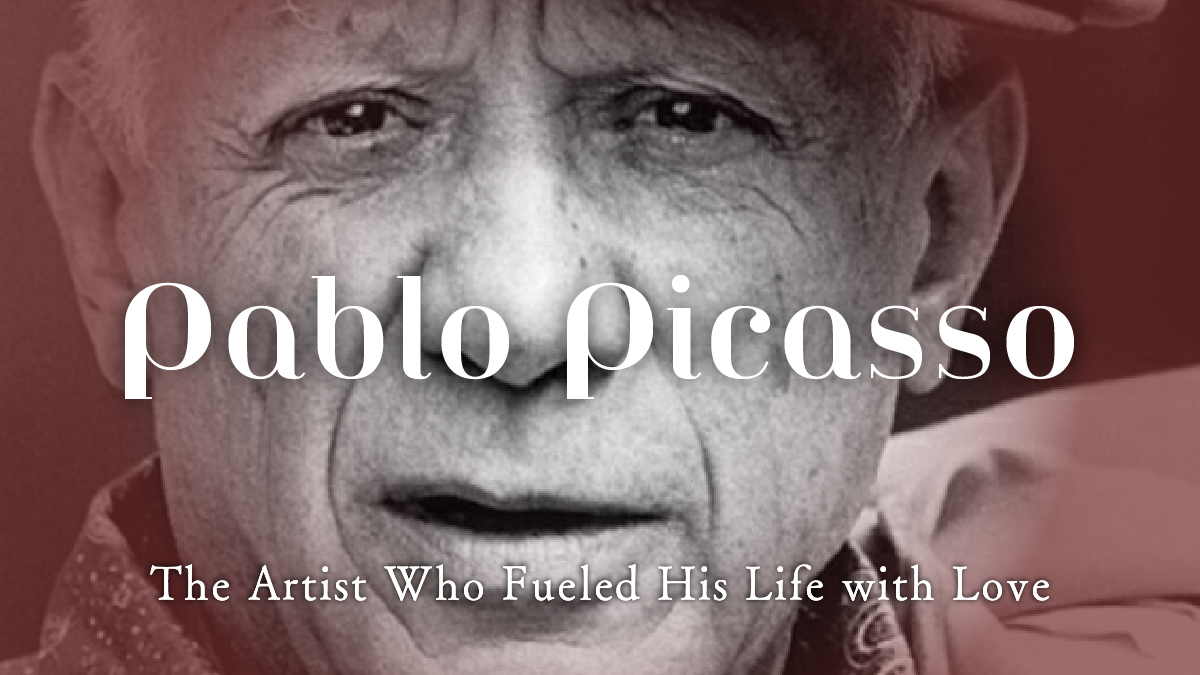
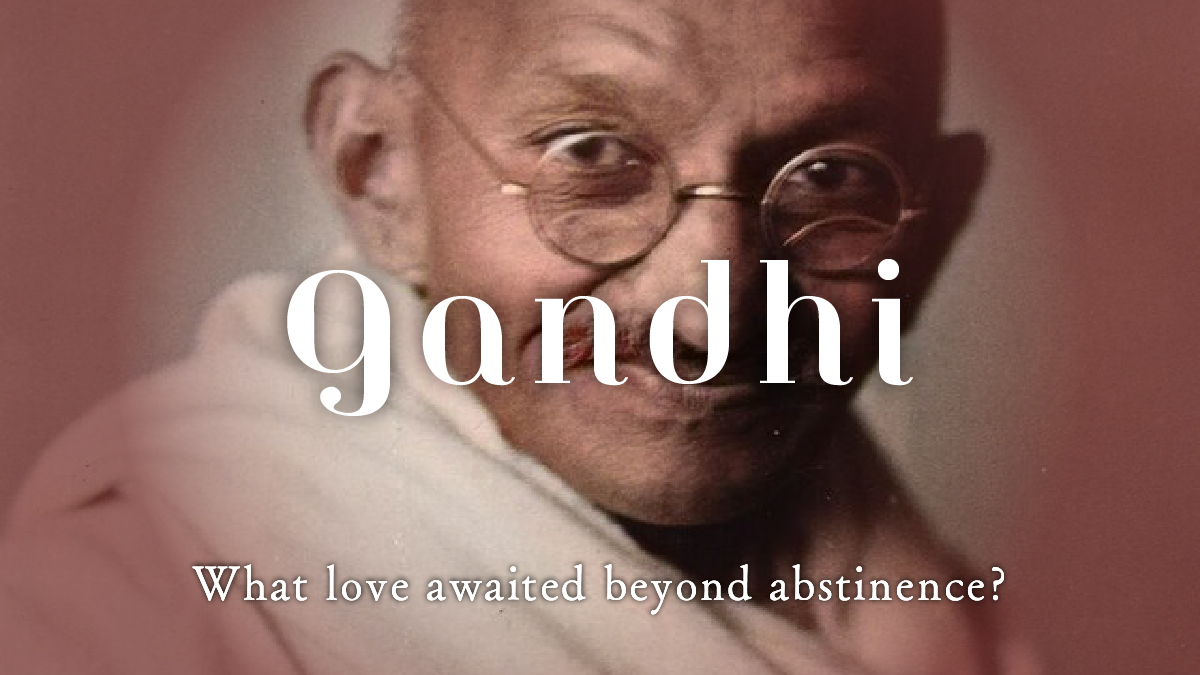

 English
English