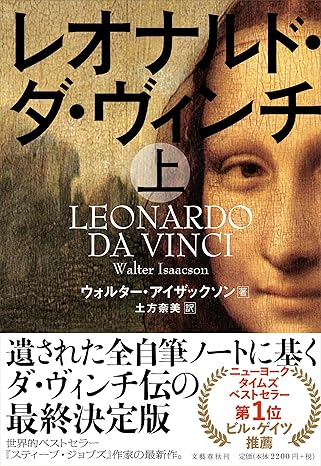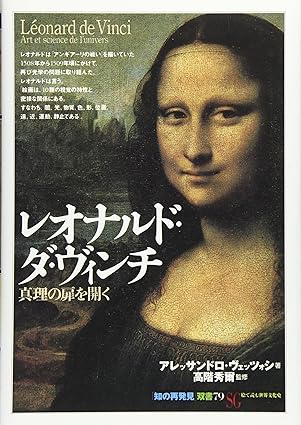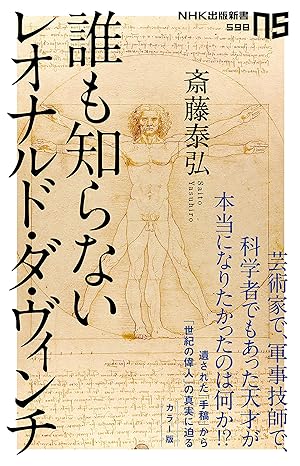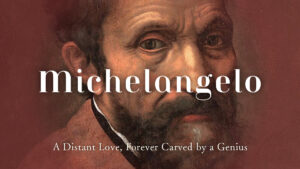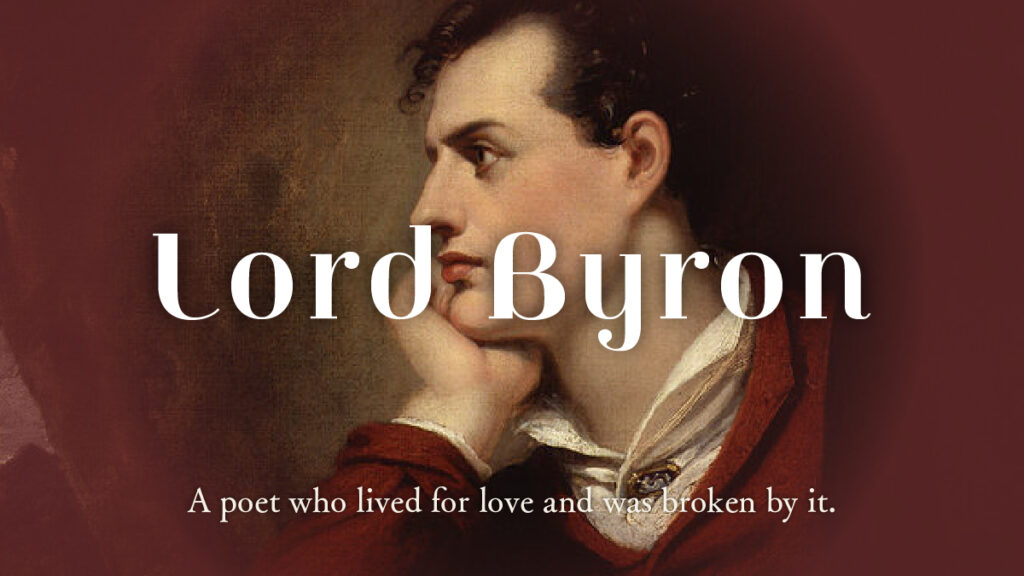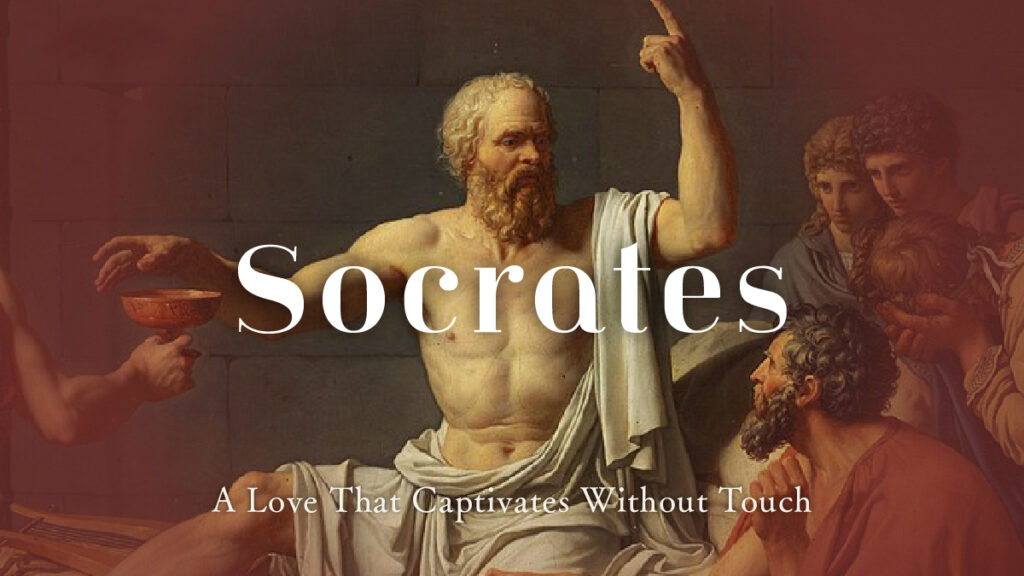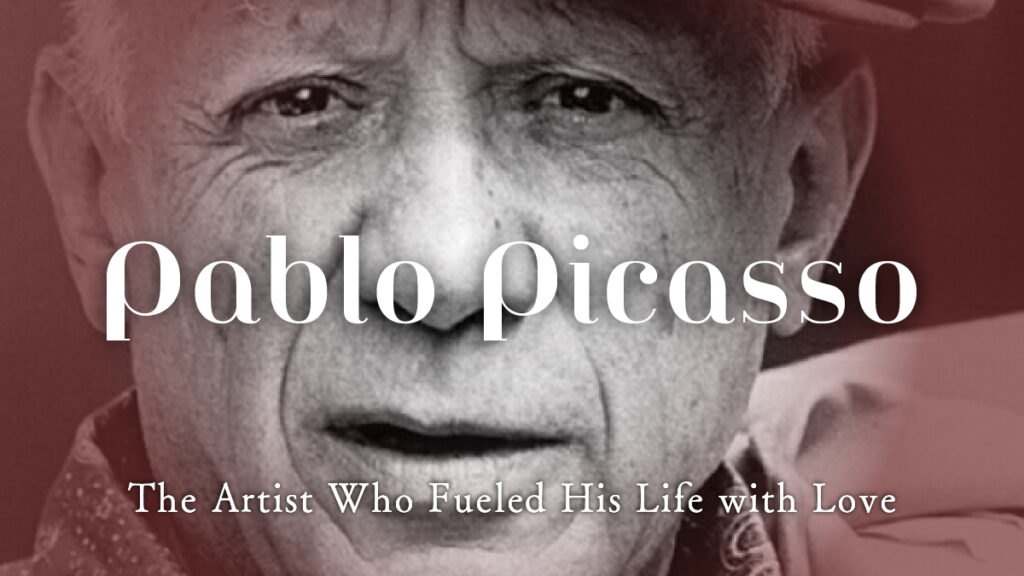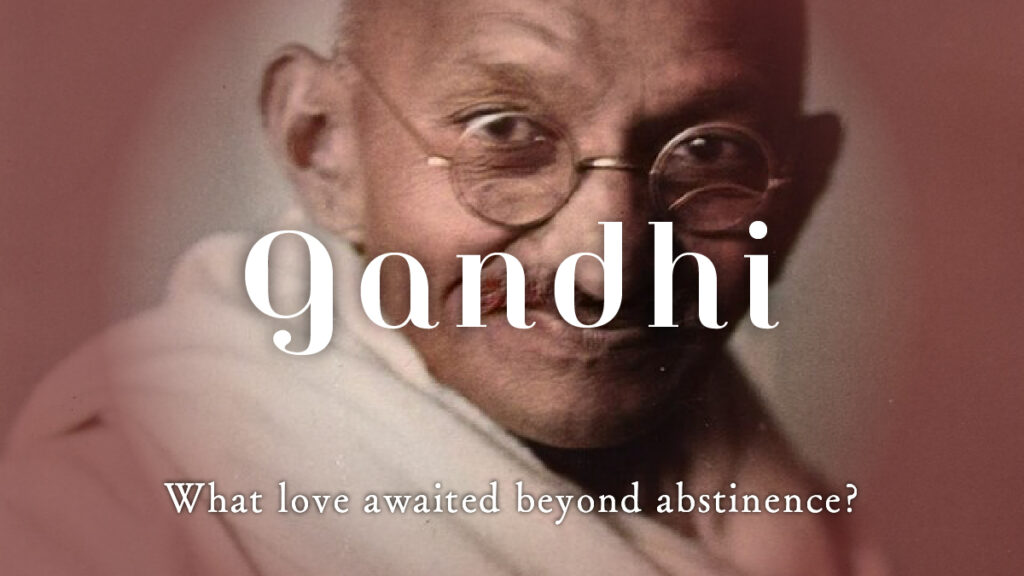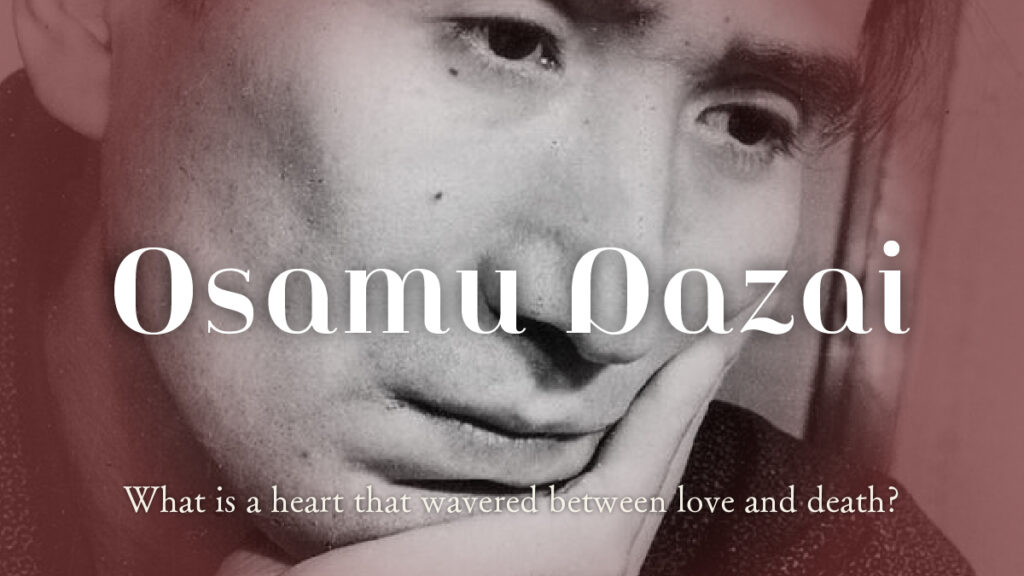レオナルド・ダ・ヴィンチの恋愛観に迫る|“万能の天才”が秘めた静かな情熱とは?
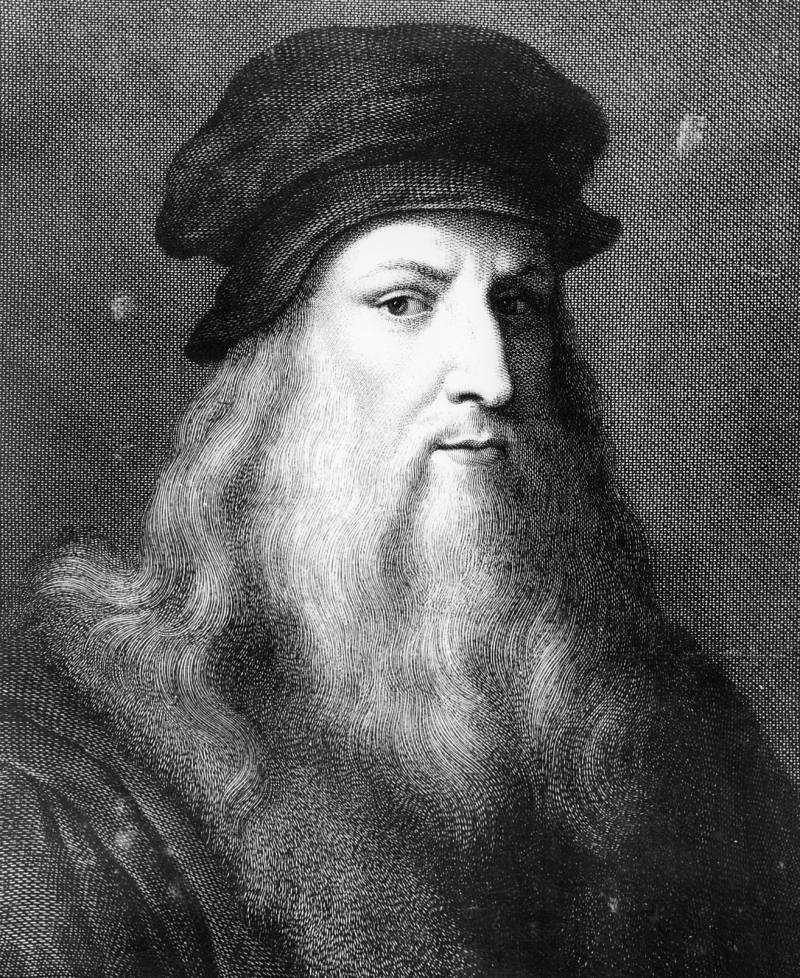
絵筆を握れば、時を止めた。
雲のように流れる髪、ふとした微笑み、そして瞳の奥に宿る魂――
それらを一瞬にして捉えるその手つきは、まるで神の息吹をなぞるようだった。
レオナルド・ダ・ヴィンチ。
1452年、イタリアのヴィンチ村に生まれ、後にルネサンスを象徴する“万能の天才”と称される男。
『モナ・リザ』『最後の晩餐』といった名画に加え、解剖学、工学、天文学…
彼の知は、あらゆる境界を越えて広がっていった。
だが、その偉業の陰で、彼はどのような恋をして、誰を見つめていたのだろうか。
語られなかった想いの輪郭を、そっとなぞってみよう。
芽吹かぬ恋の土壌
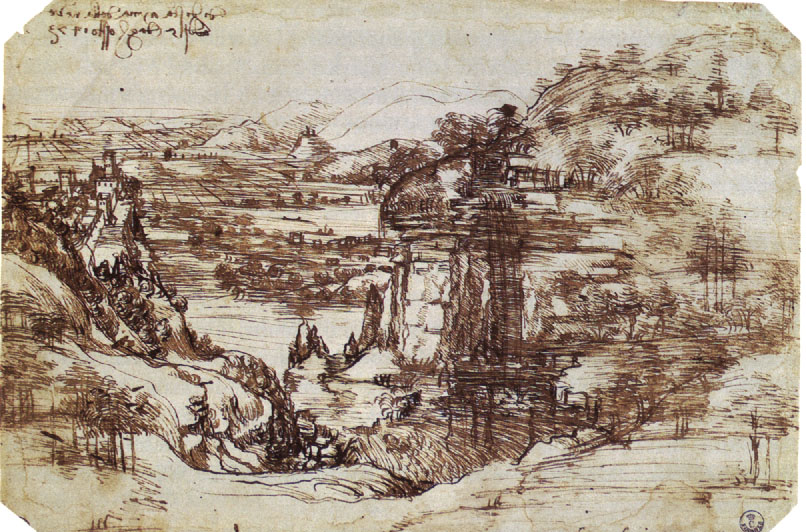
母の記憶と、始まりの孤独
1452年、婚外子としてレオナルドは誕生した。
父は公証人ピエロ、母は農家の娘カテリーナ。
幼少期を母のもとで過ごした彼は、やがて父に引き取られ、フィレンツェ近郊で育てられる。
母の影が薄れた幼少期。
それは、彼にとって「女性」という存在をどこか遠いものとさせたのかもしれない。
だが、自然の中に育った彼の眼は、木の葉のかたち、鳥の羽ばたき、水のゆらぎに魅せられた。
観察し、記録し、模倣する――彼は世界を「愛する」よりも先に「読み解く」ことに夢中だった。
恋に胸を焦がす年頃になっても、彼が魅せられたのは、肌の温もりではなく光と影の交錯する人体の構造だった。
友情の仮面を被った、揺れる感情

告発と沈黙、心の影
24歳になったレオナルドは、ヴェロッキオ工房で絵筆を握り、構図と光の魔術に没頭していた。
その静かな創作の日々を揺るがす事件が起きる。
若い男性と不適切な関係を持ったという“ソドミー”の容疑。
当時のイタリアでは、同性愛は宗教的にも社会的にも重罪であり、裁判沙汰になれば命にも関わる。
証拠不十分で不起訴となったものの、その影は彼の内面に深く差し込んだ。
愛は語るよりも、描くことなのか…。
沈黙の中で、彼は感情を絵筆に託していく。
芸術と欲望のあいだで

小悪魔との出会い
30代に入った頃、彼の前に現れたのがジャン・ジャコモ──通称“サライ”。
わずか10歳、金髪の巻き毛と整った顔立ち、そして奔放で憎めない性格。
市場で騒ぎを起こしていた彼に、レオナルドは何かを感じたのだろう。弟子として迎え入れ、自宅に住まわせるようになる。
手稿には「サライ、盗人、嘘つき、大食らい」と散々な言葉が並ぶが、それでもサライは30年にわたって彼の傍にいた。
『バッカス』や『洗礼者聖ヨハネ』などの男性像には、サライの面影が見て取れる。
芸術的研究と称される裸体画の中には、親密さと官能の気配がほのかに漂っている。
2人の関係が肉体的なものであったのか、それとも精神的な結びつきだったのか、確証はない。
だが、30年にわたり共に暮らし、叱り、愛し、描いた関係は、ただの師弟愛には収まらない。
愛か、執着か、それとも創作の女神のような存在だったのか。
答えは、サライのまなざしの奥にだけ、そっと封じられている。
静謐なる継承者との出会い
50代を迎えたレオナルドは、ミラノやローマを転々とし、芸術と科学の狭間で多忙な日々を過ごしていた。
そんな時期に出会ったのが、フランチェスコ・メルツィ。年齢わずか15歳の青年だった。
貴族の家に生まれ、容姿端麗で教養深く、何よりその静謐な知性が彼の心をとらえた。
レオナルドは、彼の中に自身の知と感性を継ぐ存在を見出したのだろう。
手稿には彼への丁寧な指示と助言が残されており、その文体からは慈しみがにじみ出ている。
『アンギアーリの戦い』など、混沌とした構図に挑む日々の中で、レオナルドの傍にはサライとメルツィの両者がいた。
前者が混乱と欲望を象徴する存在だったとすれば、後者は静けさと秩序をもたらす存在だった。
メルツィのまなざしの中に、彼は初めて無言の理解を見出したのかもしれない。
晩年の静けさと、傍らにいた青年

フランスで迎えた穏やかな最期
晩年、レオナルドはフランソワ1世の招きでフランス・アンボワーズへ移住する。
すでに右手が不自由になっていたが、メルツィとともに静かな余生を送りながら、モナリザに筆を入れ続けた。
一方で、サライはすでに独立し、イタリアで画家として活動を始めていた。
1519年、春のアンボワーズで彼は静かに息を引き取る。
その枕元には、メルツィが寄り添っていたとされ、フランス王もその死を悼んだという。
遺言には、手稿、衣服、道具など多くの遺産をメルツィに託す旨が記されており、サライには一部の家財と絵画が遺された。
葬儀はアンボワーズのサン・フロランタン教会で行われ、創造の神秘を追い求めた天才の魂は、静かにその地に眠った。
沈黙の愛と、万物を抱いた天才

愛を語らず、線の奥に封じた心
67年の生涯で、レオナルドは一度も結婚せず、恋文もスキャンダルも残さなかった。
むしろ、女性との関係においては「距離を置いていた」と言う方が正しいかもしれない。
手稿には、性交について「人間が動物的本能に堕する瞬間」と記された記述もある。
性愛を、創造や精神性と同列に置かない姿勢は、生涯一貫していた。
一部では「女性嫌い」とも囁かれたが、女性を侮蔑した記録はなく、むしろ理想化しすぎていた節すらある。
彼が描く女性たちは皆、神秘的で、現実離れした静かな微笑を湛えている。
触れることのできない存在だからこそ、永遠を与えたのかもしれない。
芸術の陰に隠された愛
レオナルドの愛は、言葉にも、触れる手にも宿らなかった。
彼が注いだのは、動き、構造、表情の中にある「生命の理」だった。
奔放なサライも、静かなメルツィも、
図面の余白やスケッチの筆致の中に、密かに息づいている。
恋を定義せず、名づけず、ただ観察する。
それが彼なりの愛の形だったのかもしれない。
彼の遺したあらゆる功績の中に、あなたはどんな愛を感じますか。
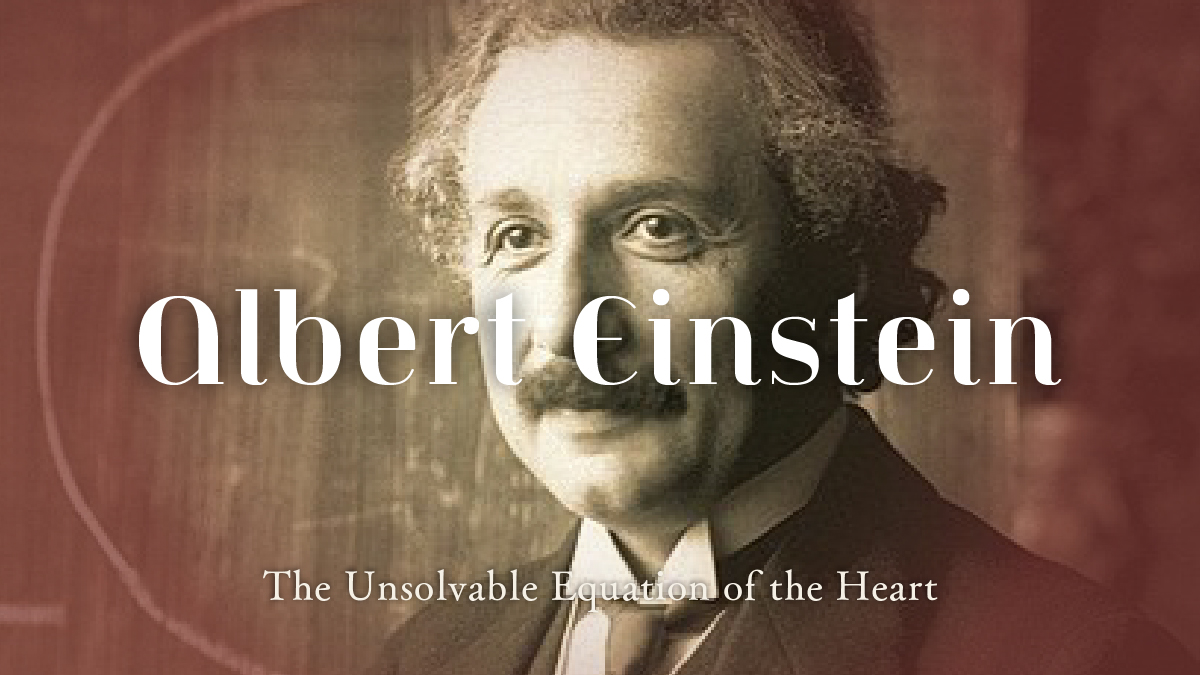



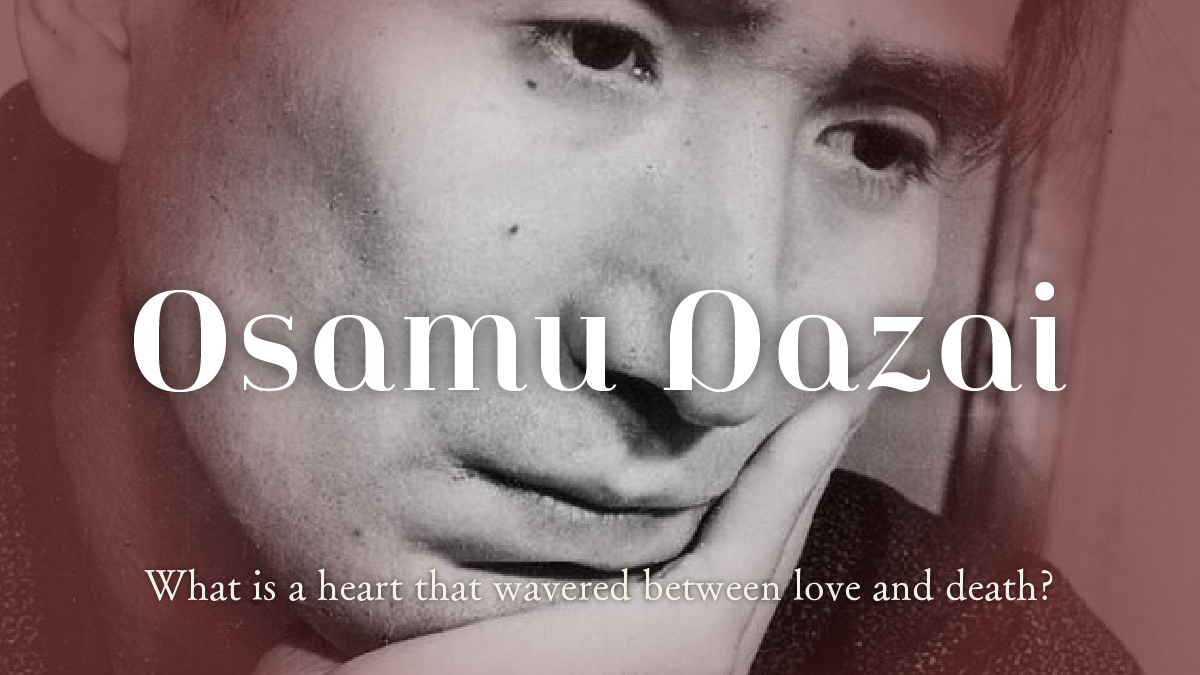
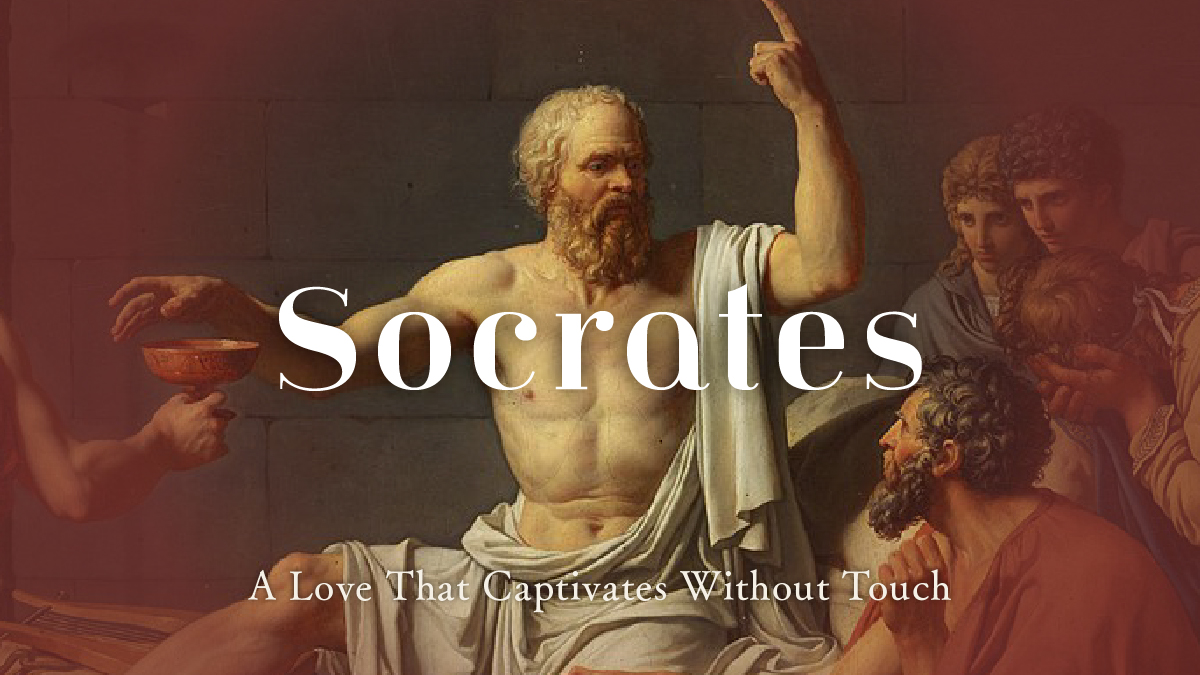

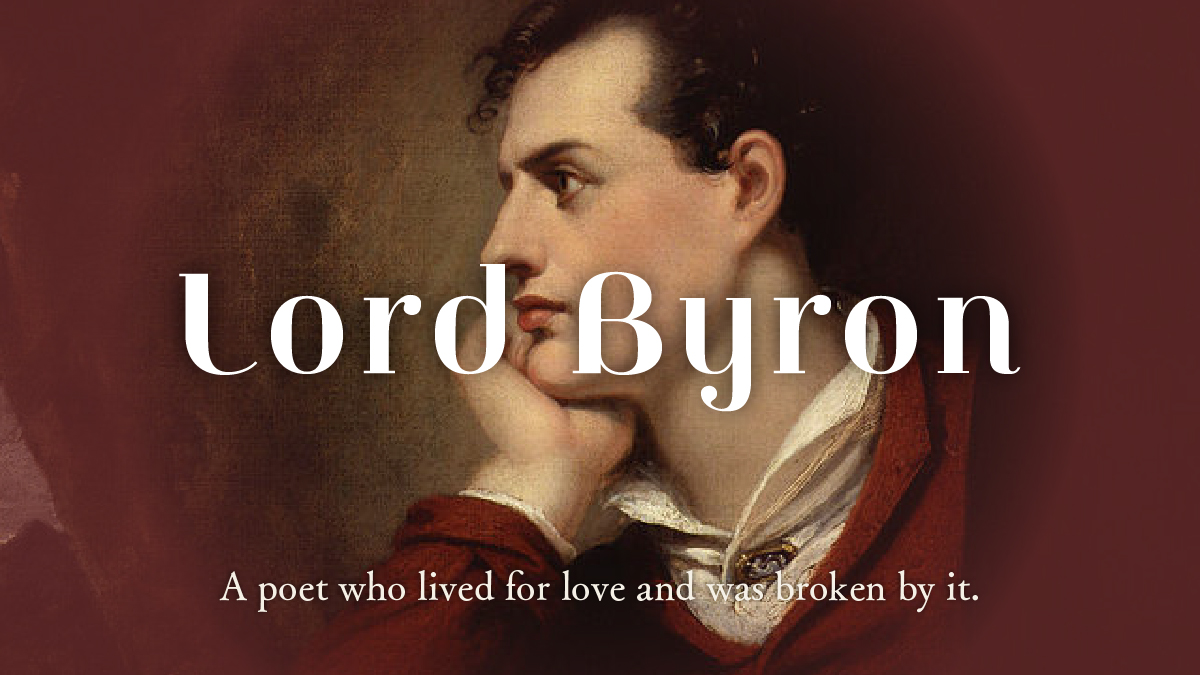





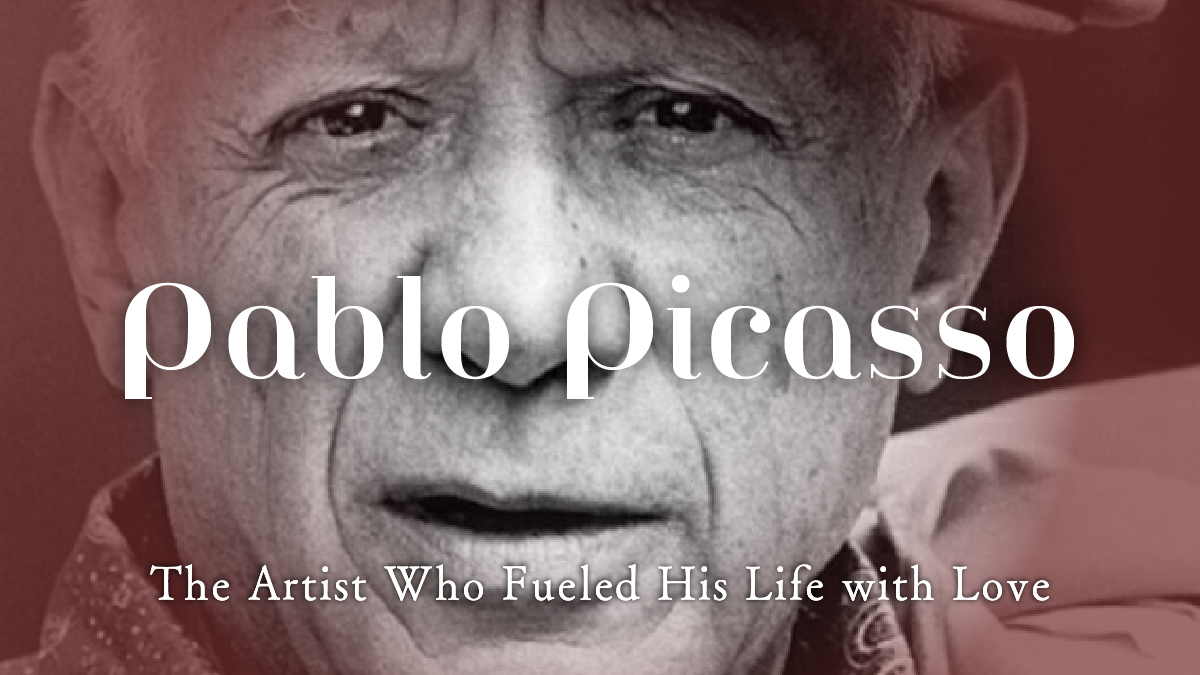
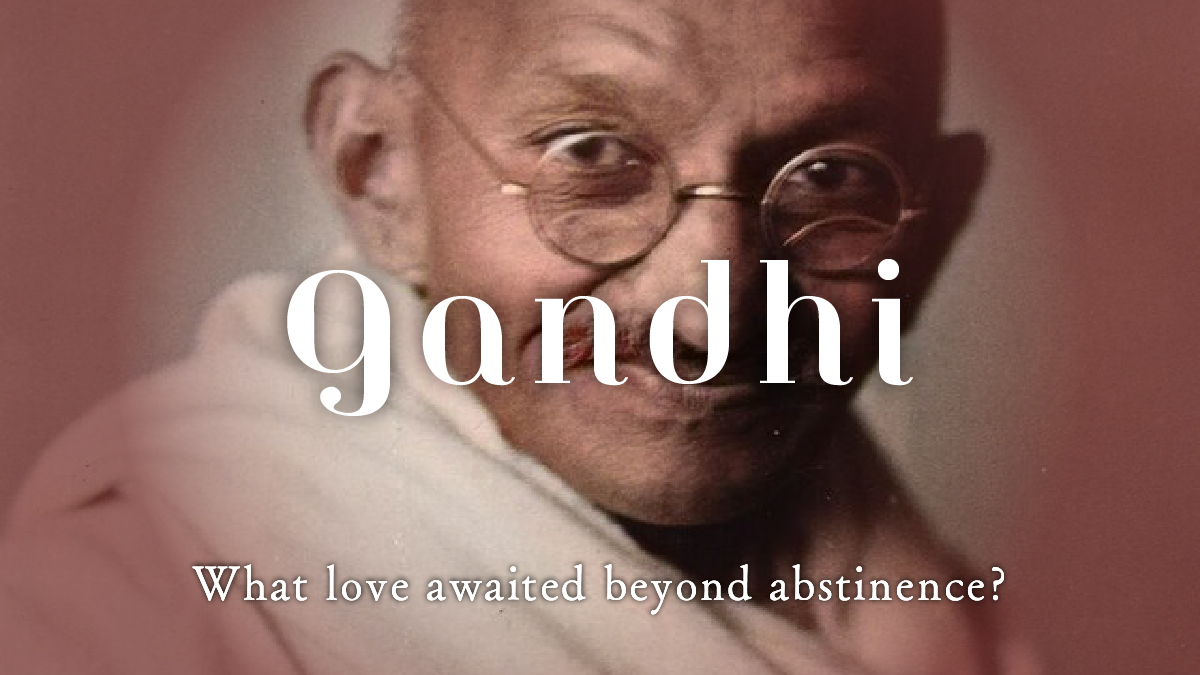

 English
English