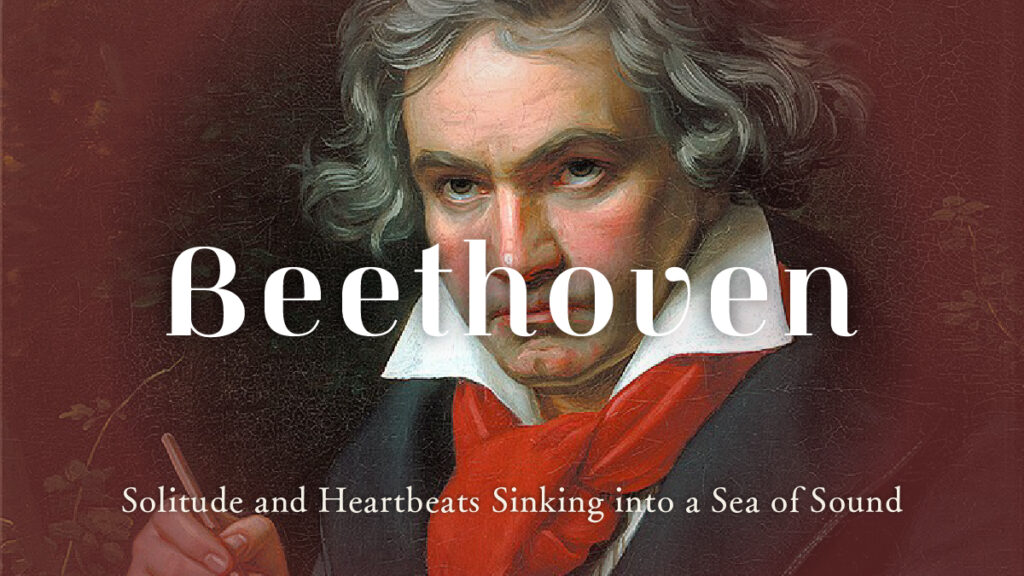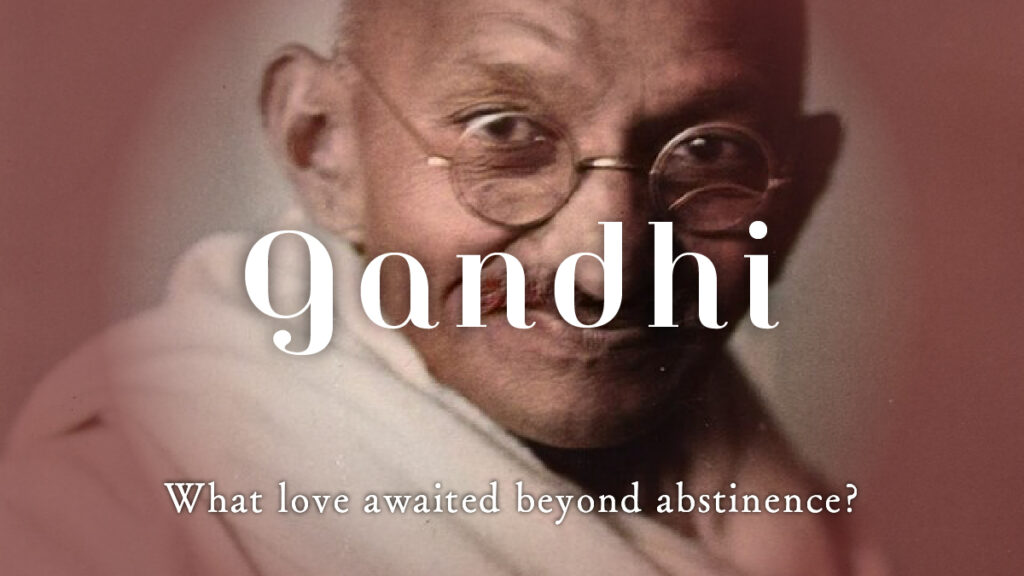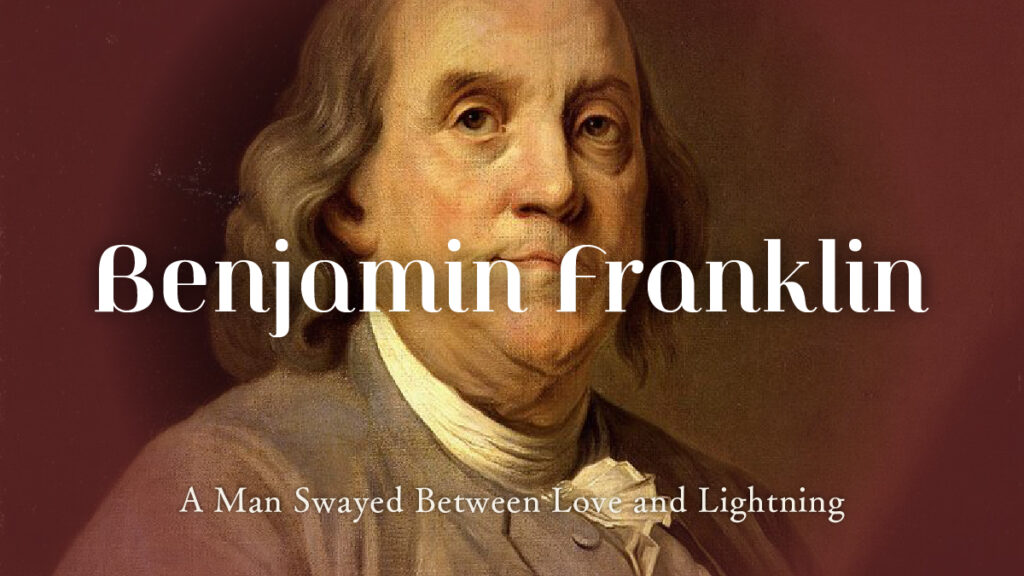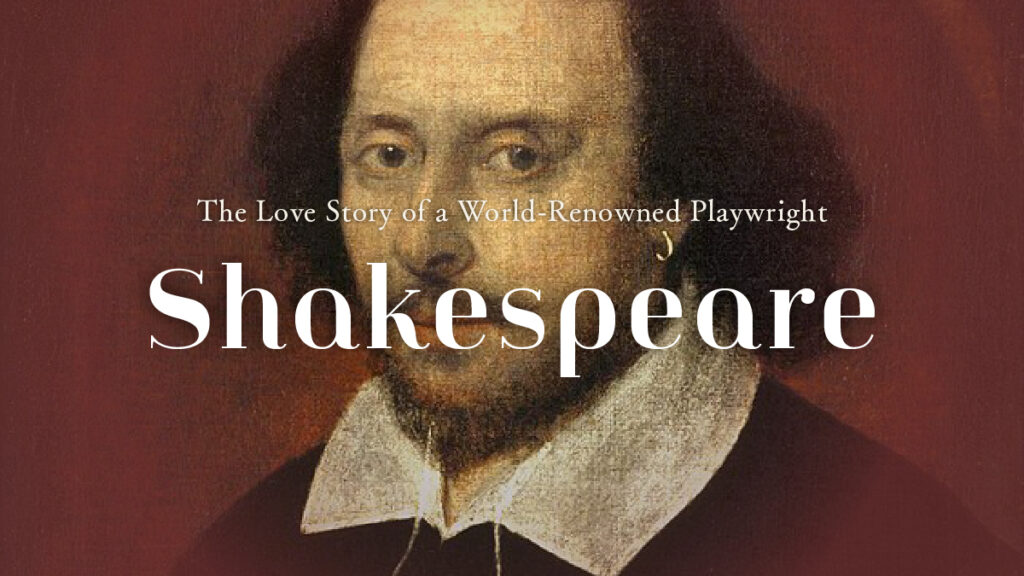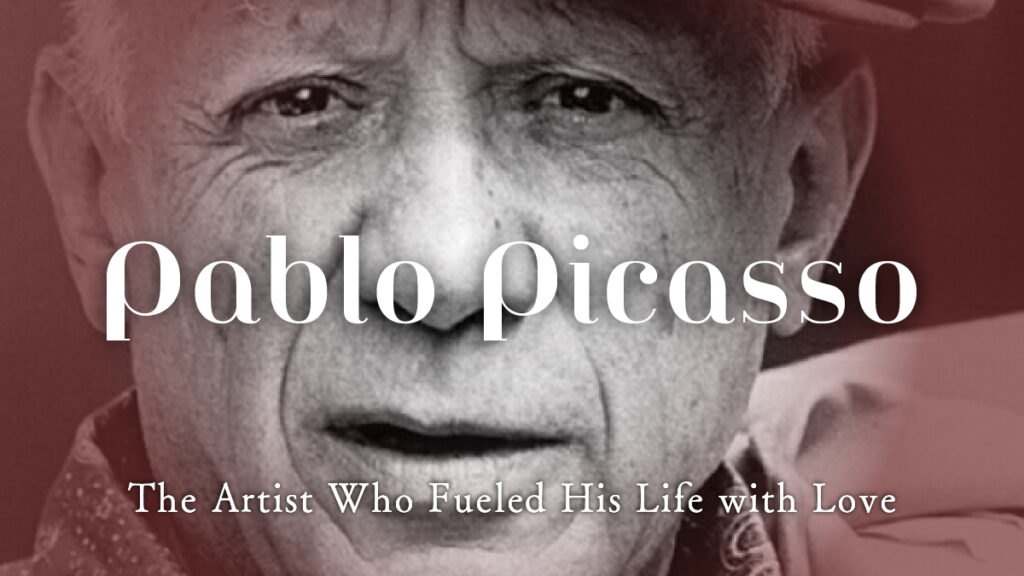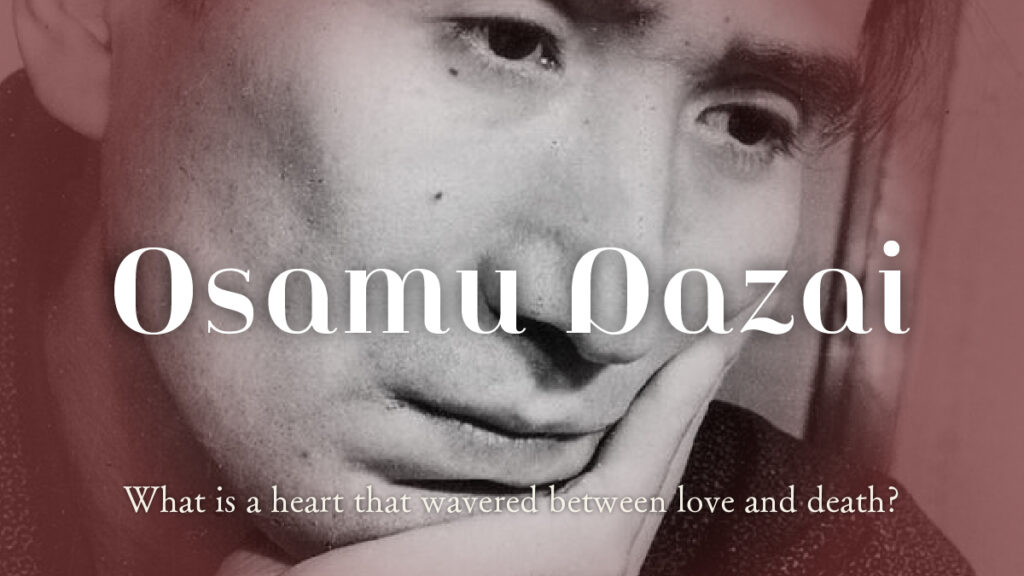ハドリアヌス帝の恋愛観に迫る|美青年に恋したローマ皇帝の真実とは?

ローマ帝国の第14代皇帝、ハドリアヌス。
イベリア半島の小さな町に生まれた彼は、やがて世界最大の帝国を治めることになる。
ハドリアヌスは、剣よりも理性と美意識を愛した皇帝だった。
エルサレムにパンテオンを再建し、英国に「ハドリアヌスの長城」を築いた――
そう、歴史の教科書にも必ず登場する偉人だ。
だが彼の名が、千年の時を超えて語り継がれてきたのは、石や鉄の遺産ばかりではない。
ハドリアヌスの人生には、もう一つの、誰もが静かに耳を澄ませるべき“物語”がある。
それは、ある美青年との恋――
帝国の栄光の陰で燃え上がった、秘められた愛の記憶を紐解いてみよう。
幼き日の孤独

学問に癒やされた少年時代
紀元76年、ローマ帝国領イタリカ(現スペイン・セビリア近郊)の裕福な家に、ハドリアヌスは生を受けた。
幼くして父を失い、やがて養父となるトラヤヌス(のちの皇帝)の庇護のもとで育つ。
剣と戦争よりも、ギリシャ文学と美術に心を寄せた少年時代。
「ギリシャびいき」と揶揄されても、彼は詩や哲学、彫刻に夢中になった。
やがて青年期を迎えると、ハドリアヌスは軍隊生活も経験することになる。辺境の地で兵士たちと寝食を共にし、規律や現場の空気を身をもって学んだ。
この時期、彼の恋愛の記録は何ひとつ残されていない。
けれども、孤独な日々に文学のなかで理想の「美」を探し続けていたのかもしれない。
皇帝としての愛 ― 歴史の裏に隠れた恋

帝位継承、そしてサビナとの結婚
ハドリアヌスが24歳のとき、彼の人生は大きく動き出す。
養父トラヤヌスが皇帝に即位し、ハドリアヌスもまた、帝位継承者としての運命を背負うこととなった。
その重圧のさなか、彼は貴族出身の娘・ウィビア・サビナと結婚する。
ふたりが出会ったのはハドリアヌスが20代前半、サビナはおそらく10代半ば――美しく気高い、ローマの良家の令嬢だった。
政略結婚――それはローマ帝国の常であり、個人の幸福や心のときめきよりも家名と権力が優先された。サビナもまた、ハドリアヌスとの結婚に自らの夢や希望を託してはいなかっただろう。
けれど、記録によればサビナは知的で自立心が強く、皇后としての誇りを忘れなかった。彼女はローマ市民からも敬意を集め、公共事業や慈善活動に尽力したと伝えられている。
だが、夫婦としてのふたりはどうだったか。
ハドリアヌスは宮廷では公正で理知的な皇帝だったが、家庭では寡黙で冷ややかだったとされる。
サビナは夫の無関心や距離に心を痛めていたとも言われ、「夫は私に愛情を注いでくれない」と周囲にこぼしたという逸話も残る。
それでも、ふたりは表向きには理想的な“皇帝と皇后”を演じ続けた。
子どもは授からず、やがて夫婦の間に感情の隙間が広がっていったが、サビナは最後まで皇后としての責務を果たし、威厳と知性を保ちながら自分なりの生き方を貫いた女性だった。
夫婦として深く踏み込むことはなかったものの、ハドリアヌスはサビナの名誉や立場を損なうことは決してしなかった。
お互いに干渉しすぎず、“大人の距離感”を保った婚生活――
そこには時代と身分に翻弄された二人の姿があった。
現場主義と美意識の皇帝
ハドリアヌスは“現場主義”の皇帝として知られている。
ローマ宮廷に安住することなく、帝国全土を自らの足でくまなく旅し、兵士や地方の人々とも直接会話した。
ときには素性を隠し、庶民の暮らしぶりをこの目で確かめるほど好奇心旺盛だった。
宿営地でも美術や詩、哲学書を手放さず、テントの片隅で巻物を広げ、星空を眺めながら物思いにふける夜も多かったという。
また、ハドリアヌスは無骨な武力よりも、ギリシャ文明の理知と美を愛した文化系皇帝でもあった。
パンテオン再建やハドリアヌスの長城は、軍事施設や宗教建築であると同時に、彼の美意識と合理主義が息づく都市設計として後世に語り継がれている。
軍人としての厳しさと、芸術家のような繊細さ――
その二面性こそが、ハドリアヌスという皇帝を唯一無二の存在にしていた。
秘密と光、そして終わりのない喪失

巡遊の途上で出会った“運命”
“旅する皇帝”の人生に、ある日思いがけない出会いが訪れる。
紀元123年頃、ハドリアヌスが帝国の東方、アジアのビテュニア地方――現在のトルコ西部――を旅していたときのこと。ひとりの美しい少年が、皇帝の人生を静かに、しかし決定的に変えていくことになる。
その名はアンティノウス。
出会ったとき、彼はまだ15歳ほどの、あどけなさの残る青年だった。
アンティノウスは、その容姿もさることながら、内に秘めた繊細さと静かな聡明さで、ハドリアヌスの心に火を灯した。
出会った瞬間から、二人のあいだには言葉を超えた“なにか”が流れた。
二人は旅の道連れとなり、宴の席でも、狩りの夜でも、あるいはローマの浴場でも、常に寄り添い合うようになる。
宮廷の誰もが二人の親密さに気づいていた。
ローマ社会では、年長の男性と若者の精神的・肉体的な結びつきが“美徳”として語られることもあったが、皇帝という立場でその愛を貫くには大きな覚悟が必要だった。
やがて、ふたりの関係は下世話なゴシップとして広まった。
「皇帝は美少年に夢中だ」――
そんな声が、石畳の町にも広がっていった。それでもハドリアヌスは怯まず、アンティノウスとともに過ごす時間を選び続けた。
ハドリアヌスは、アンティノウスに詩を捧げ、彫像を作らせ、その美をコインにも刻ませた。
帝国の権力者と無名の青年――ふたりの年齢差は30歳。
けれども、ふたりの間には、身分や常識を超えた親密さが静かに芽生えていった。
アンティノウスはときに不安げなまなざしで、時に無垢な笑顔でハドリアヌスを見つめ返した。
皇帝の心は、帝国の広さよりも遥かに大きな空虚を埋めていったに違いない。
ナイルの悲劇
ローマ皇帝と美青年――
ふたりの旅路は、エジプトで思いがけない終幕を迎える。
紀元130年、ハドリアヌスとアンティノウスはナイル川を遡る旅に出た。ピラミッドの影に満月が昇る夜、ナイルの水面には静かな揺らぎが広がっていたという。
だが、幸福な時間は永遠には続かなかった。
その年、アンティノウスはわずか18歳の若さで、ナイル川にその身を沈める。
死の理由はいまも謎に包まれている。
「生贄として神に捧げられた」
「皇帝への絶対的な愛ゆえに命を絶った」
さまざまな説が飛び交ったが、真相は永遠に闇の中だ。どの説にも、哀しみと愛が静かに滲む。
ハドリアヌスはその死を知るや、涙を隠すことなく嘆き悲しんだという。帝国の主が人前で涙を流したのは、これが最初で最後だったかもしれない。
悲しみのなか、ハドリアヌスはアンティノウスのために「アンティノウポリス」という都市を建設し、アンティノウスを神として公式に崇拝させた。
ローマの皇帝が“愛する者を神格化”したのは極めて異例のことだ。
愛した者を神にする――
それは、権力者にして孤独な人間、ハドリアヌスの愛のかたちだったのだろう。
晩年の孤独――愛の余韻と皇帝の黄昏

権力の頂で見つめた“欠落”
アンティノウスを失ったハドリアヌスは、かつての覇気をどこかに置き忘れてしまったかのようだった。
帝国の広大な版図も、金銀財宝も、かつて彼を彩った宮廷の賑わいすら、心の空洞を埋めることはできなかった。
政治に目を向ければ、かつての冷静で理知的な判断は健在だったが、晩年のハドリアヌスは孤独の影を纏っていた。
詩や建築に没頭し、アンティノウスの面影を追い求めて過ごす日々。
サビナとの関係は冷め、そばには静かな忠臣と、石に刻まれた美少年の微笑みだけが残された。
時折、夜の宮殿で一人、彼は月を仰ぎながら考え込んだという。得たものと失ったもの、その均衡がどれほど儚いものであるかを、誰よりも知っていたからだろう。
「わたしは幸せを求めていたが、それが何かを知らなかった」
ハドリアヌスが語ったとされるこの言葉には、皇帝としての孤独、そして人としての愛への渇望が滲んでいる。
紀元138年、62歳のとき、病に倒れた彼は、静かに人生の終わりを受け入れた。
最期の瞬間、誰の名を呼んだかは記録に残っていない。
ハドリアヌス帝の恋愛観とは?
ハドリアヌスの生涯は、理性と情熱、美と孤独が複雑に絡み合った軌跡だった。
パンテオンを再建し、帝国の秩序を整えたその知性の裏には、ひとりの人間として「愛」を求める繊細な心があったのかもしれない。
皇帝として、彼は世界を掌に収めた。だが、愛する者を失ったとき、彼は初めて「支配できないもの」があることを知った。
アンティノウスを神に昇華させたのは、愛を永遠に閉じ込めるためだったのか、それとも喪失に抗う祈りだったのか――。
ハドリアヌスにとって“愛”とは、手に入れるものではなく、時間を超えて残すものだったのだろう。
あなたなら、愛する者を失ったとき、忘れようとするだろうか。
それとも、彼のように永遠へと刻もうとするだろうか。
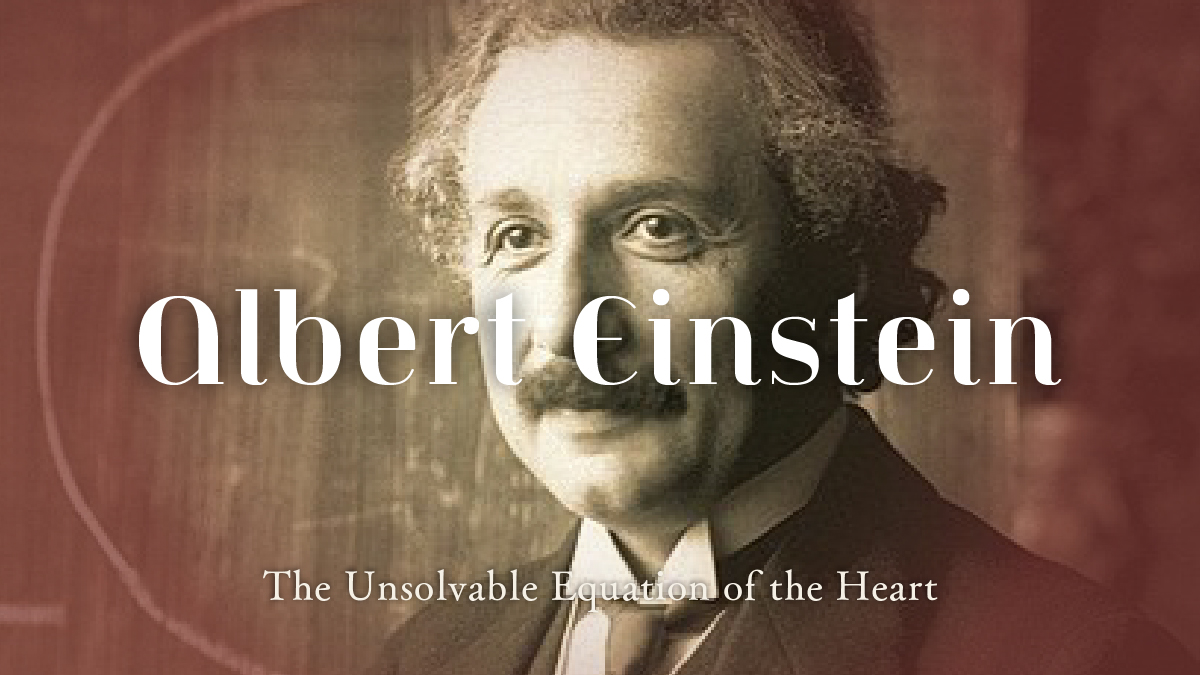



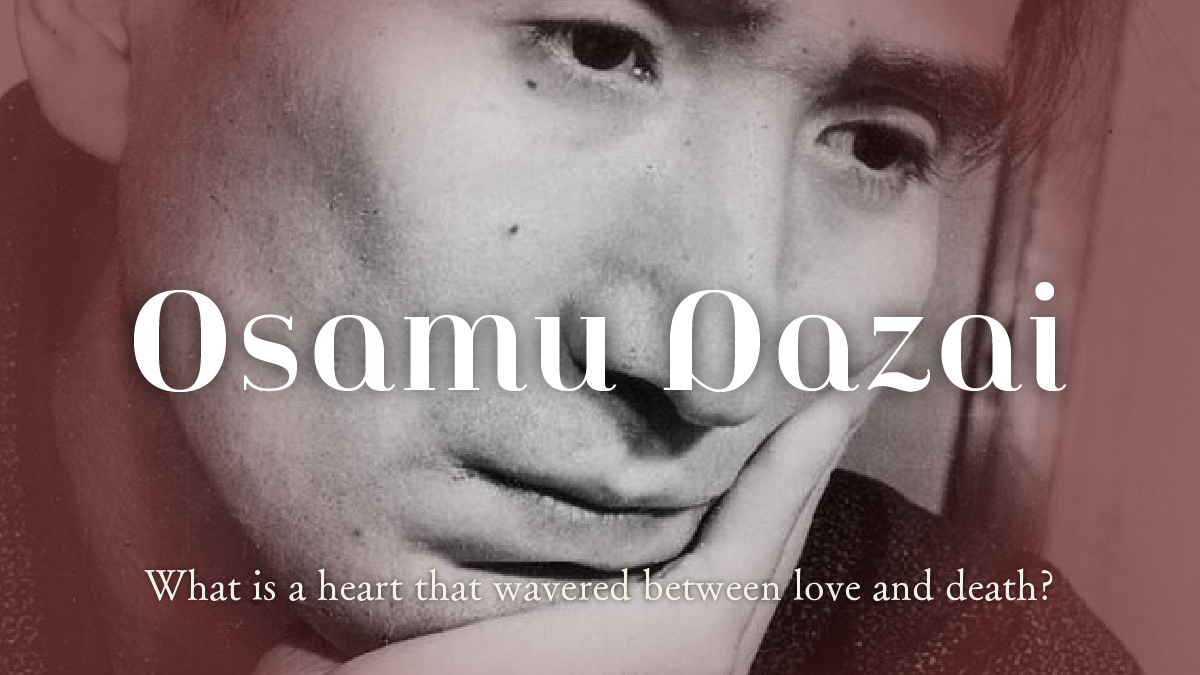
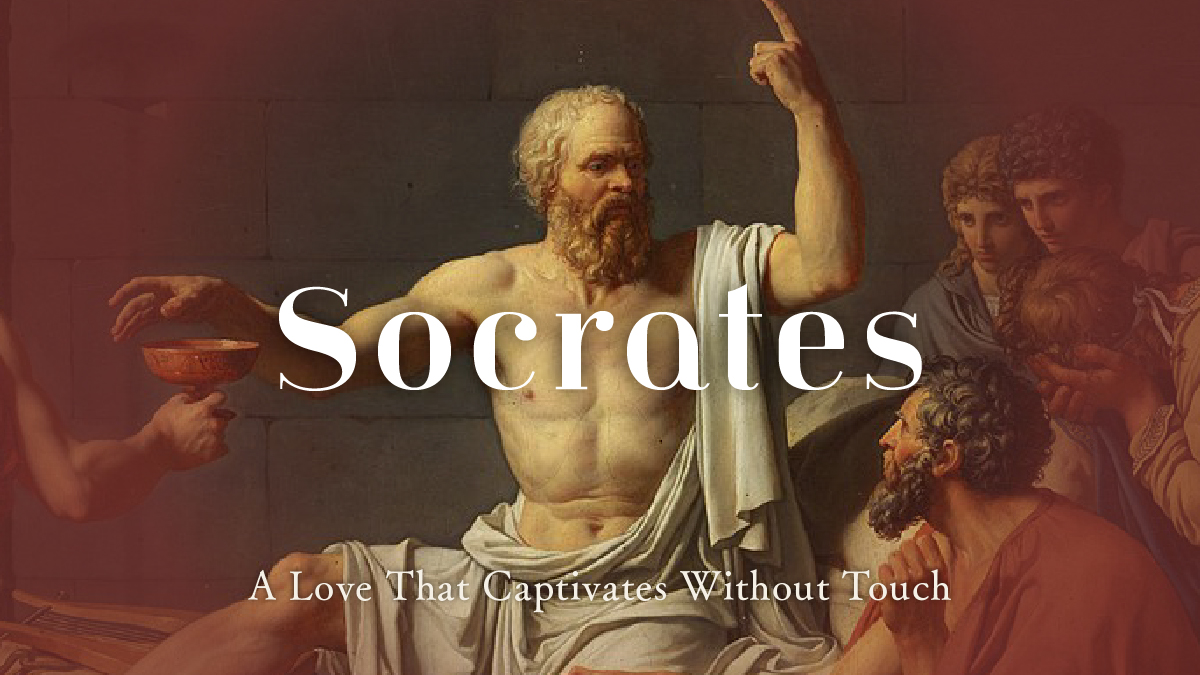

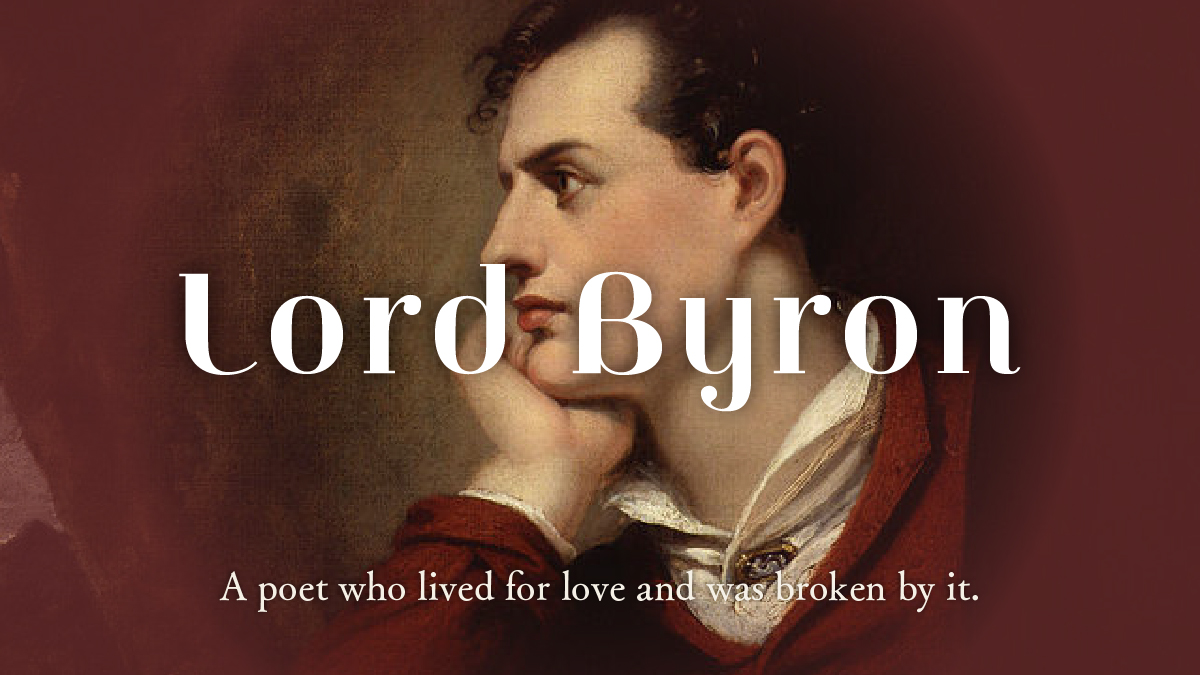





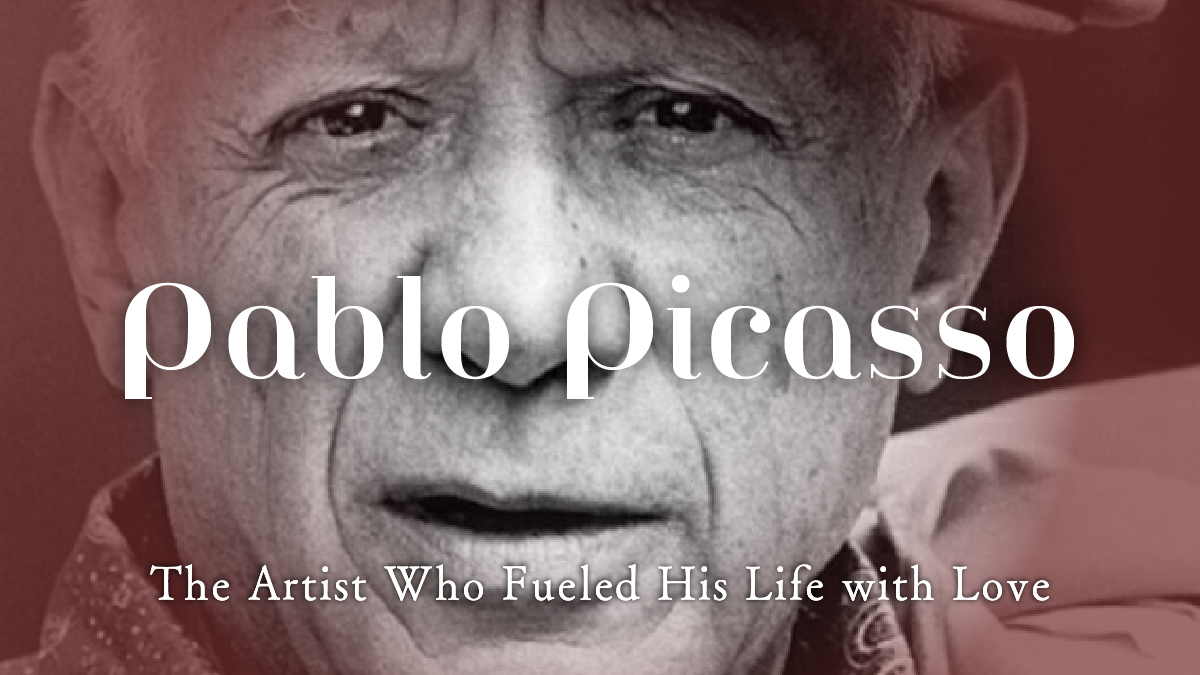
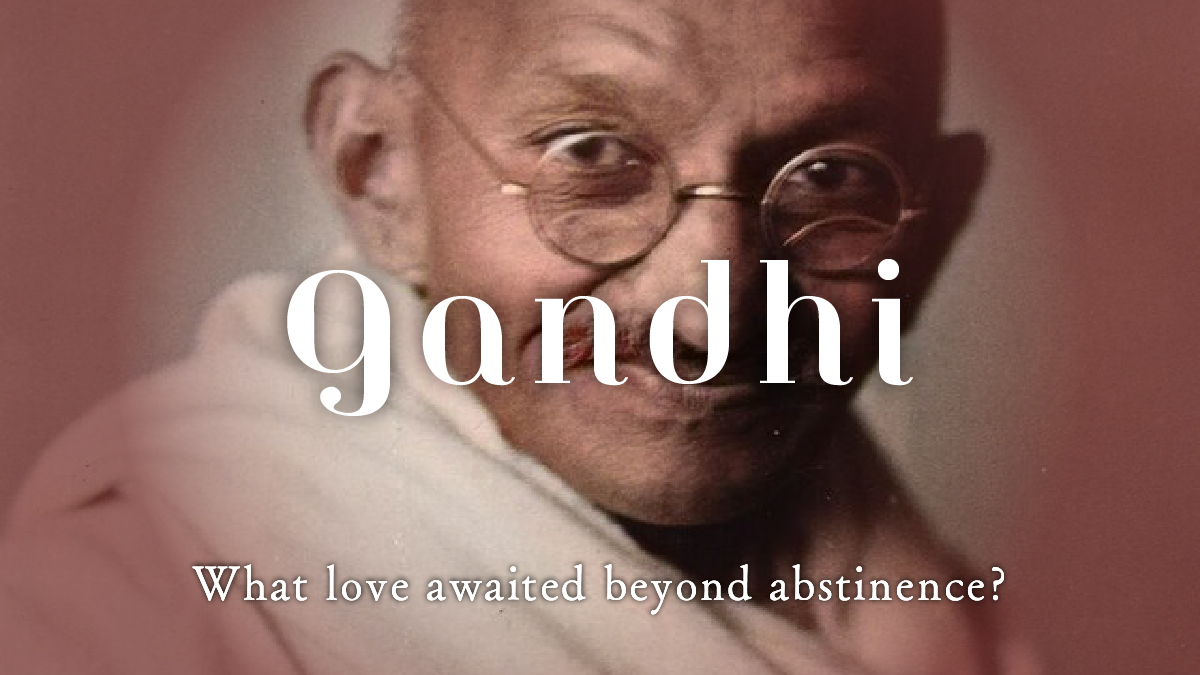

 English
English