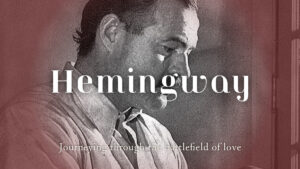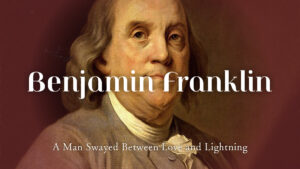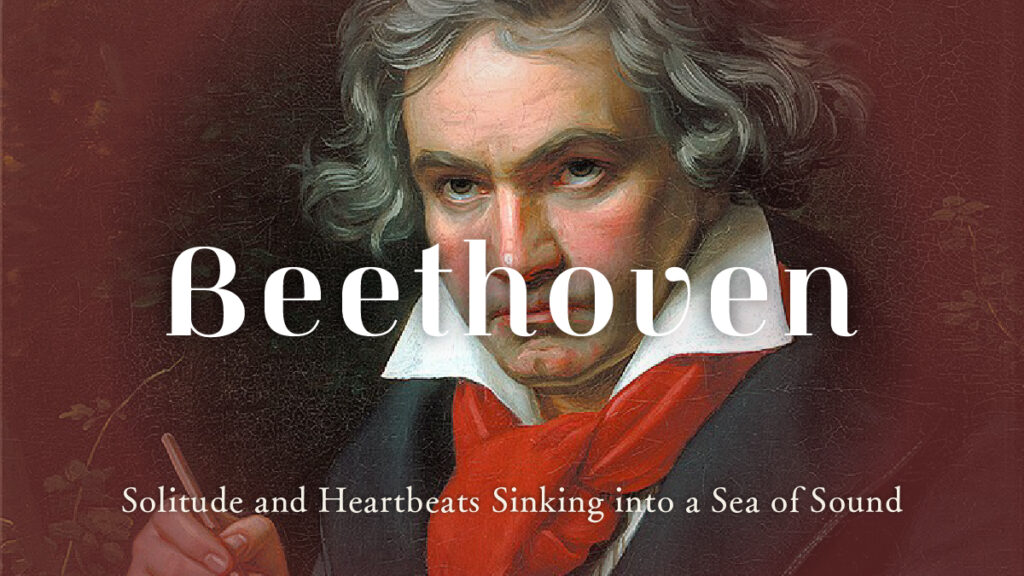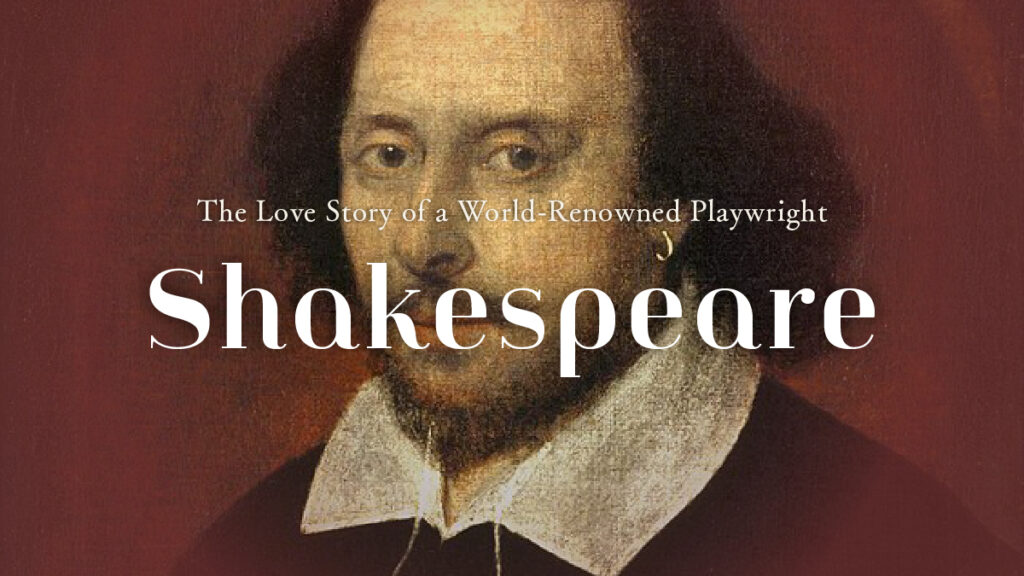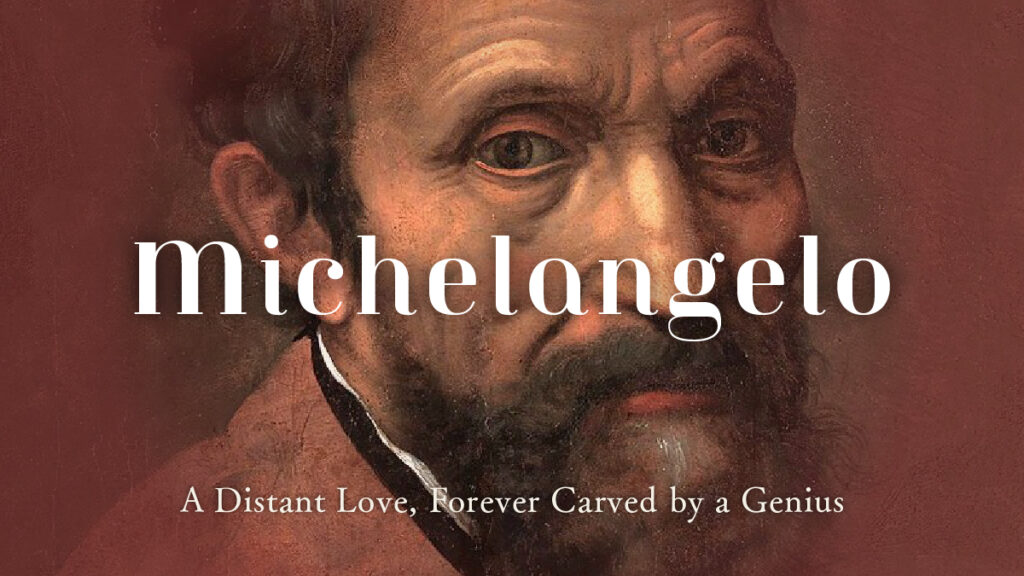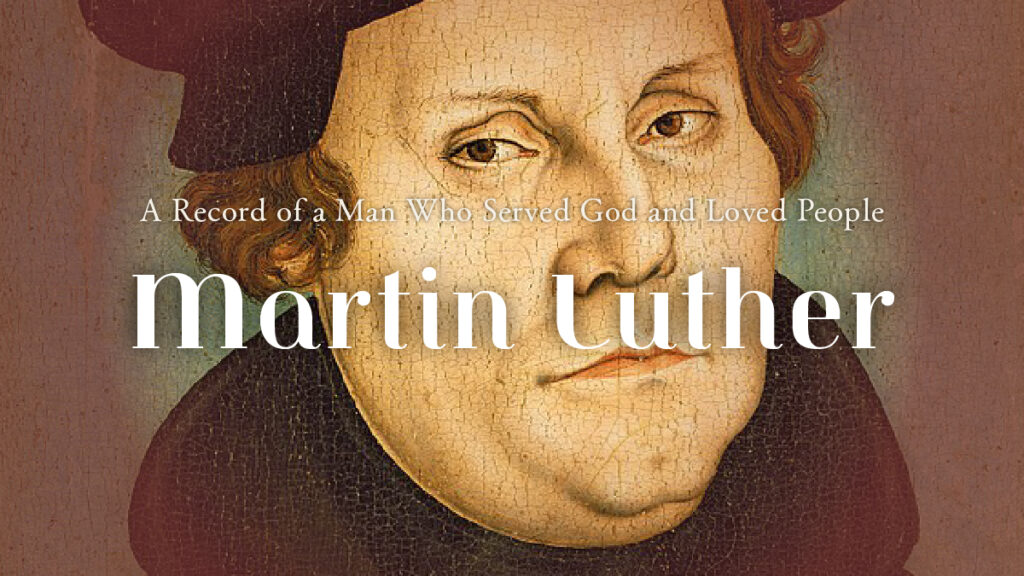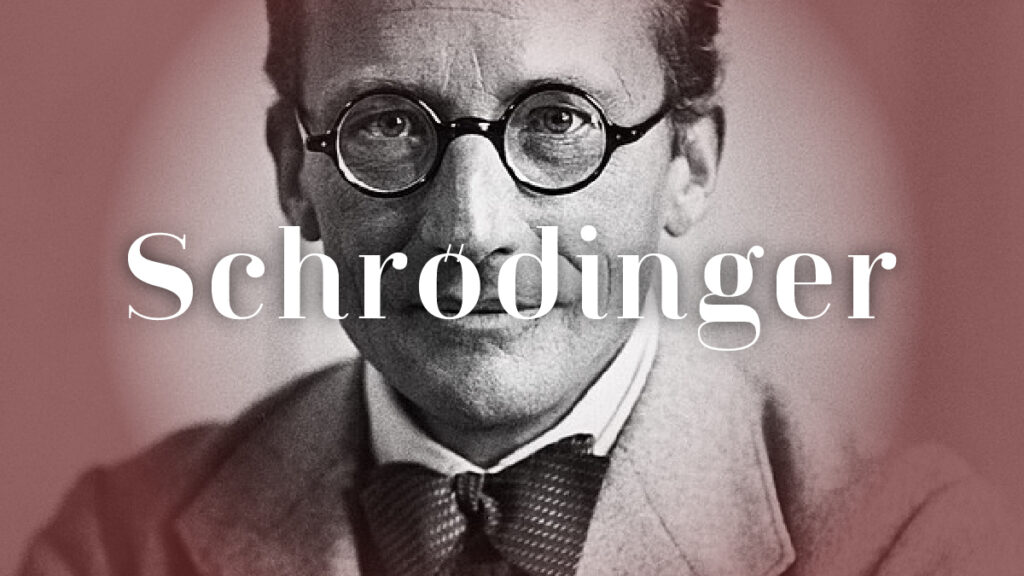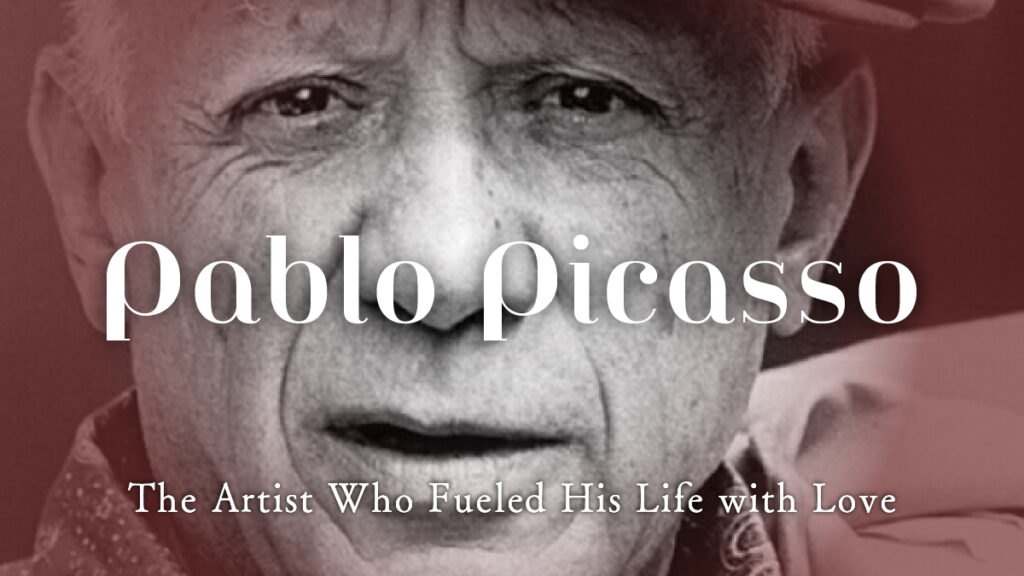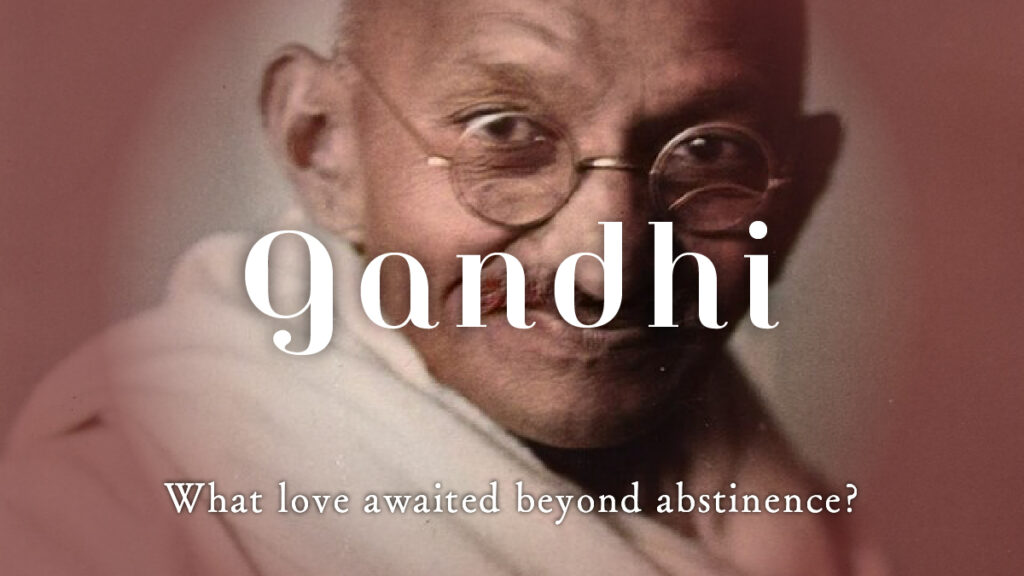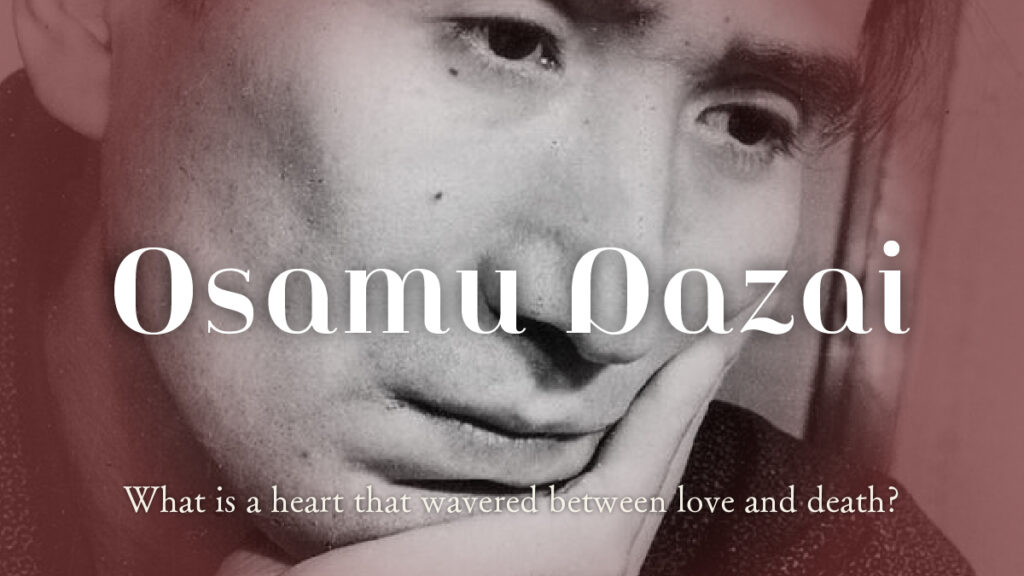ソクラテスの恋愛観に迫る|“哲学の父”が語った触れずに奪う愛とは?

「無知の知」を説き、問答を通して真理を探る――
その独特な対話法で、後世に計り知れない影響を与えた哲学者。
彼の名は、ソクラテス。
プラトンやアリストテレスへと受け継がれる西洋哲学の礎を築いた人物である。
裸足にぼろ布をまとい、通行人に問いかけながら、言葉の迷宮へと誘う。言葉を武器に、沈黙を照らす灯火のような存在だった。
人々は彼を嘲り、恐れた。
だがその声の奥には、知を超えてなお、心を震わせる“愛”の響きがあった。
本記事では、哲学者ソクラテスの“恋愛観”に光を当て、彼が語り、そして生きた“愛のかたち”をたどっていく。
少年期のまなざし

魂の助産師になるまで
ソクラテスの少年時代については多くを語る記録が残っていない。
だが、断片的な情報から浮かび上がるのは、すでに彼が“見る”という行為に敏感だったことだ。
父は彫刻家であり、母は助産師。
彫刻とは、内側から形を掘り出す作業であり、助産とは、見えない命をこの世に導く仕事だ。
「私は母と同じだ。ただし、肉体ではなく魂の助産婦なのだ」
そう語った彼の言葉は、少年期の影のような記憶を思わせる。
問いを重ねることで相手の中から“何か”を生まれさせる。
若き日のソクラテスは、武芸や体育にも通じていたとされる。
だが、戦いや競技よりも、人の表情の揺れや、言葉に潜む沈黙の気配に惹かれていたのではないか。
愛とは、美とは、魂とは——。
少年のまなざしは、いつしか問いの光を宿すようになっていった。
結婚と不機嫌な妻

クサンティッペという嵐
二人の出会いや馴れ初めについては記録が乏しいが、彼女はソクラテスよりもかなり若く、哲学者としての名が知れ渡ったあとの結婚だったとされる。
恋愛と聞いて思い浮かぶのは、甘い囁きやとろけるような夜かもしれないが、ソクラテスの家庭にはそんな情緒はない。
彼の妻クサンティッペは、「悪妻」として有名だ。
ある時クサンティッペは、ソクラテスに向かって激しくまくしたてた。
だが、彼がまるで動じないことに苛立ち、ついに“尿瓶”の中身を頭から浴びせかけたという。
それでもソクラテスは平然と、
「雷の後には雨が降るものだ」
と冗談めかして語ったらしい。
まるで自然現象を受け入れるように、夫婦の嵐もまた哲学の一部だったのかもしれない。
また、ある日アカデメイアの若者が「先生、なぜあんなに恐ろしい女性と結婚されたのですか?」と聞いた。
ソクラテスは笑いながらこう答えた。
「人生にはどんな経験も必要だ。結婚すれば忍耐を学べるし、離婚すれば自由を知る」
それは恋というより、共に生きることへの洞察。
愛がときに不協和音を含むとしても、それもまた「真理への道」と考えていたのかもしれない。
少年愛という文化

同性愛が文化だった時代
古代ギリシャでは、年長の男が少年と精神的な交わりを持つ「パイデラスティア(少年愛)」が文化として存在していた。
現代の倫理観とは大きく異なるが、当時は教育や精神修養の一環として肯定的に受け入れられていた。
ソクラテスも多くの若者に慕われた。
クリトン、フェイドン、アポロドロス……彼の周囲には常に若い魂が集まっていた。
だが、彼は師として彼らを導く役割に徹していた。そこに性的な関係があったという記録はない。
それどころか、彼の恋愛観は「いかに欲望に打ち勝つか」という問いの実践でもあった。
ある若者が、「先生、あなたはなぜ我々の愛を受け入れてくれないのですか」と涙ながらに尋ねたとき、ソクラテスはこう答えたという。
「愛とは、手に入れるものではない。手放さずに見つめ続けるものなのだ」
それは、肉体ではなく精神を焦点に置いた恋愛観の極致だった。
アルキビアデスの暴露
アルキビアデスはソクラテスの弟子であり、政治家としても名を馳せた美青年だった。彼はソクラテスに恋していた。
酒に酔ったアルキビアデスが「この肉体を献上する」と言ってソクラテスの膝に身を投げたところ、ソクラテスは静かに毛布をかけ、
「寒いだろう、風邪を引くよ」
とだけ言ったという。
彼は肉体に手を出さず、相手の魂に向き合った。
ソクラテスは「欲望」を否定しなかったが、それに流されることを“愚か”とした。
それは、哲学者としてのプライドであり、また一人の人間としての美学でもあったのかもしれない。
そして、アルキビアデスはその拒絶によって、かえって深く惹かれていった。
「肉体に触れずに、心を奪う男」——それがソクラテスだった。
愛の対話に宿る哲学

「愛とは何か?」
ソクラテスの恋愛観を語るうえで欠かせないのが、プラトンの対話篇『饗宴(シンポシオン)』である。
この作品は、酒宴の席で男たちが順に「愛とは何か」を語り合うもので、
ソクラテスはそのなかで、師である女性ディオティマから聞いた“愛の哲学”を披露する。
「愛は、美そのものを求めて魂を上昇させる力である」
そう語るソクラテスにとって、愛とは単なる肉体的な結びつきではなく、
人間が“真の美”へと至るための道標だった。
この考えは後の「プラトニック・ラブ」の礎となった。
だが、それは決して“性”を否定するものではなかった。
むしろ、肉体の魅力を肯定したうえで、それを超えていこうとする意志の表れだった。
ある夜、ソクラテスは若い彫刻家にこんなふうに語ったという。
「君の美しさは見事だ。だがその魂が見えるまでは、私の関心は始まらないのだよ」
美を愛しながらも、それに縛られない。この矛盾に満ちた態度こそ、ソクラテスの愛の核心だった。
死に際に語ったもの

最期に語られた愛
ソクラテスは毒杯を仰ぎ、静かに死を迎えた。
紀元前399年、民主政のもとで裁かれた哲学者は、「若者を堕落させた罪」により死刑となった。
死に際して彼は怒りも悲しみも見せなかった。
ただ一言、「アスクレピオスへの鶏を忘れずに」と弟子に告げて、この世を去った。
アスクレピオスは古代ギリシャ神話に登場する「医神」である。
当時、病が治った者は感謝の印として神殿に鶏を捧げる習慣があった。
この言葉の真意は定かではないが、「自分はようやく“癒された”」という心境、
すなわち、死を一種の解放・魂の自由として捉えていたと解釈されている。
欲望に溺れず、ただ真理を愛し、人を愛した男。
その人生は静かに幕を閉じた。
ソクラテスの恋愛観とは?
「無知の知」とは、知らないということを肯定すること。
ソクラテスは、それを恋愛にも適用した。
相手を知ろうとすること。自分を知ろうとすること。欲望に正直でありながら、支配されないこと。
それは、恋に落ちるたびに少しずつ賢くなっていく、そんな感覚に近い。
ソクラテスの恋愛観は、甘くもなく、派手でもない。
けれど、その静かな問いかけは、
「あなたの愛は、ただ欲しいだけの愛ではありませんか?」
そう耳元でささやくように、彼の声が時を越えて忍び寄る。
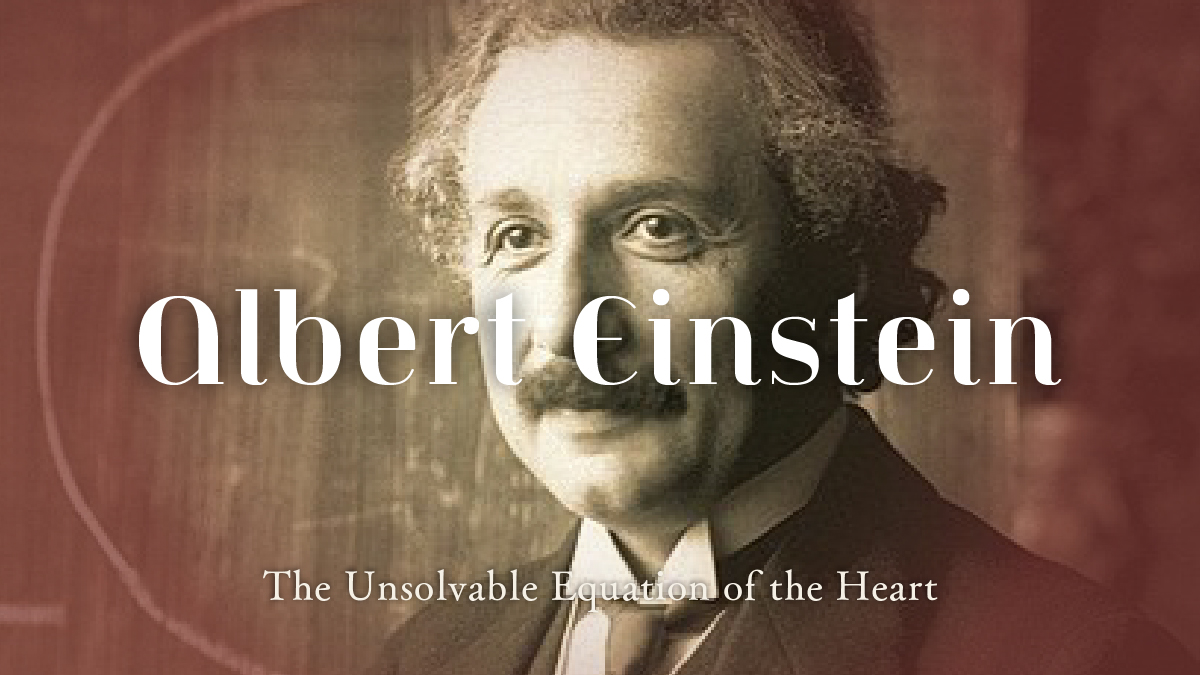
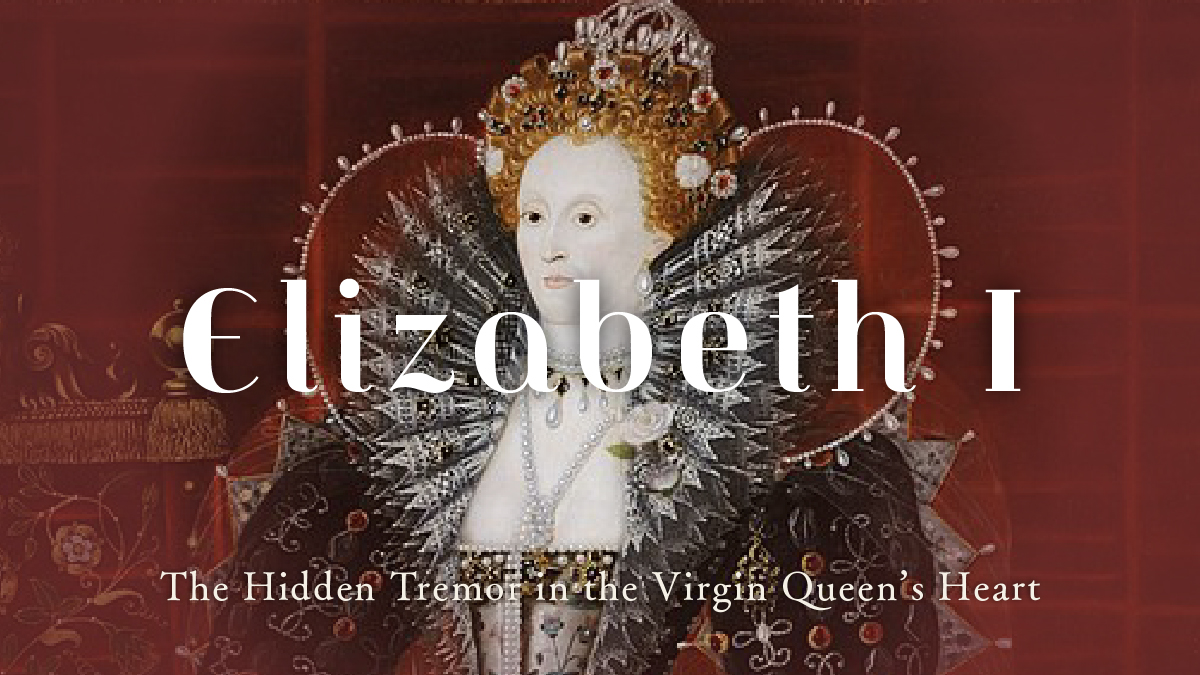
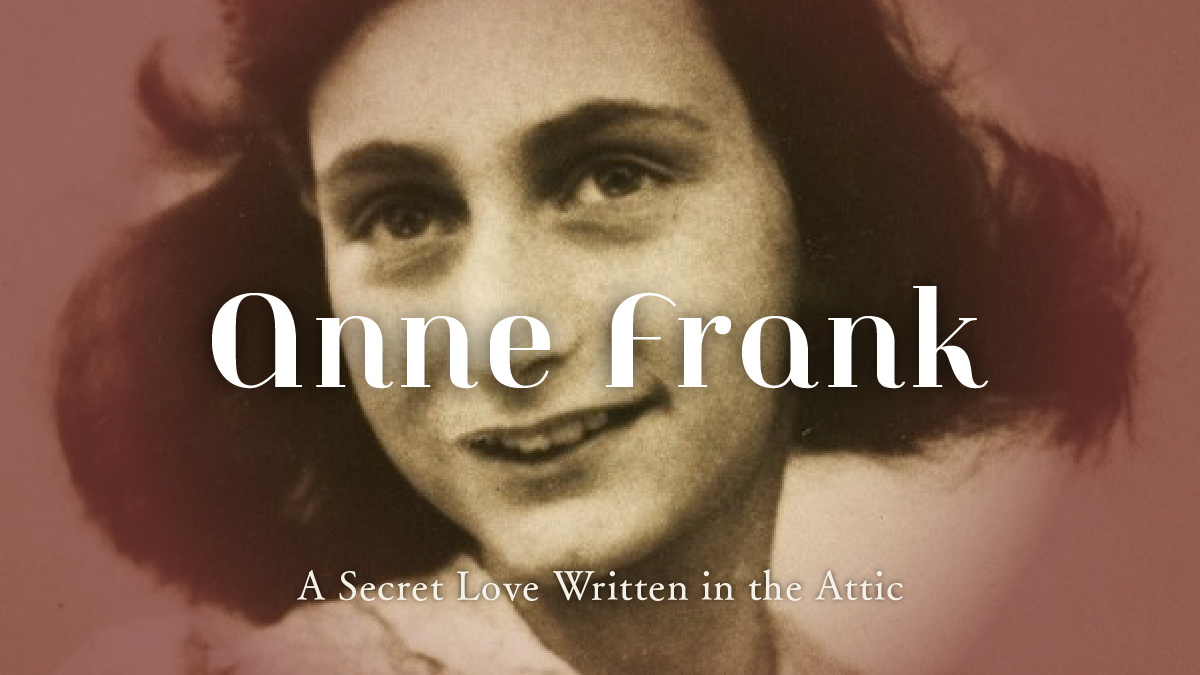
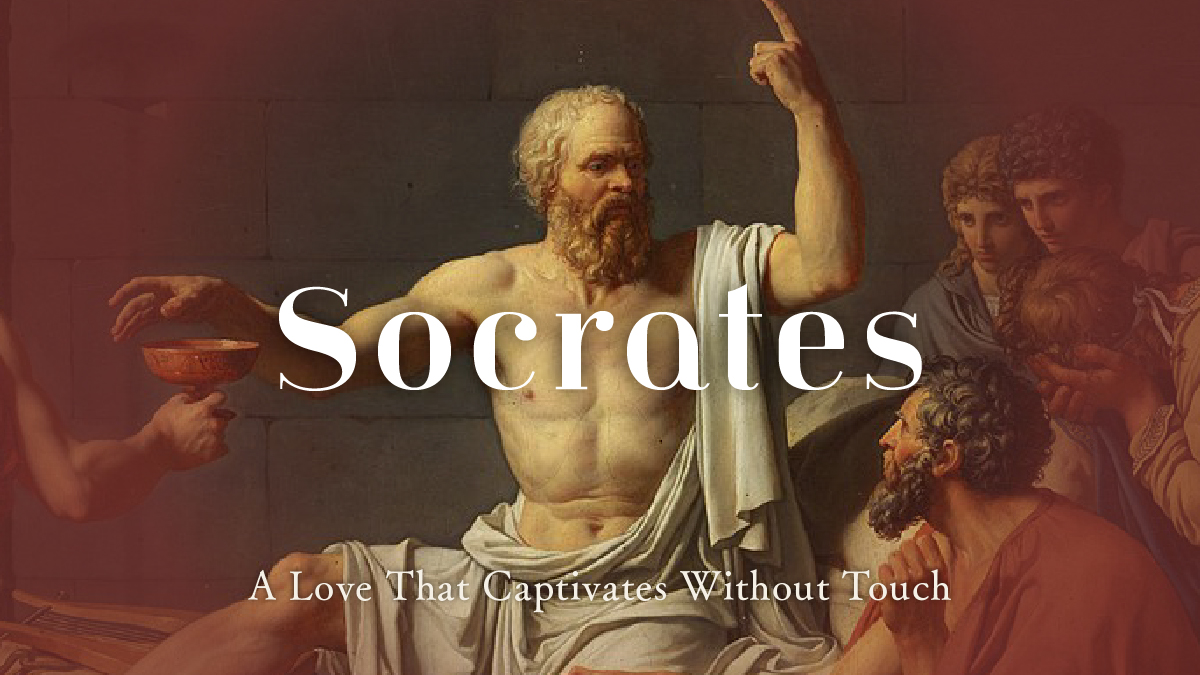

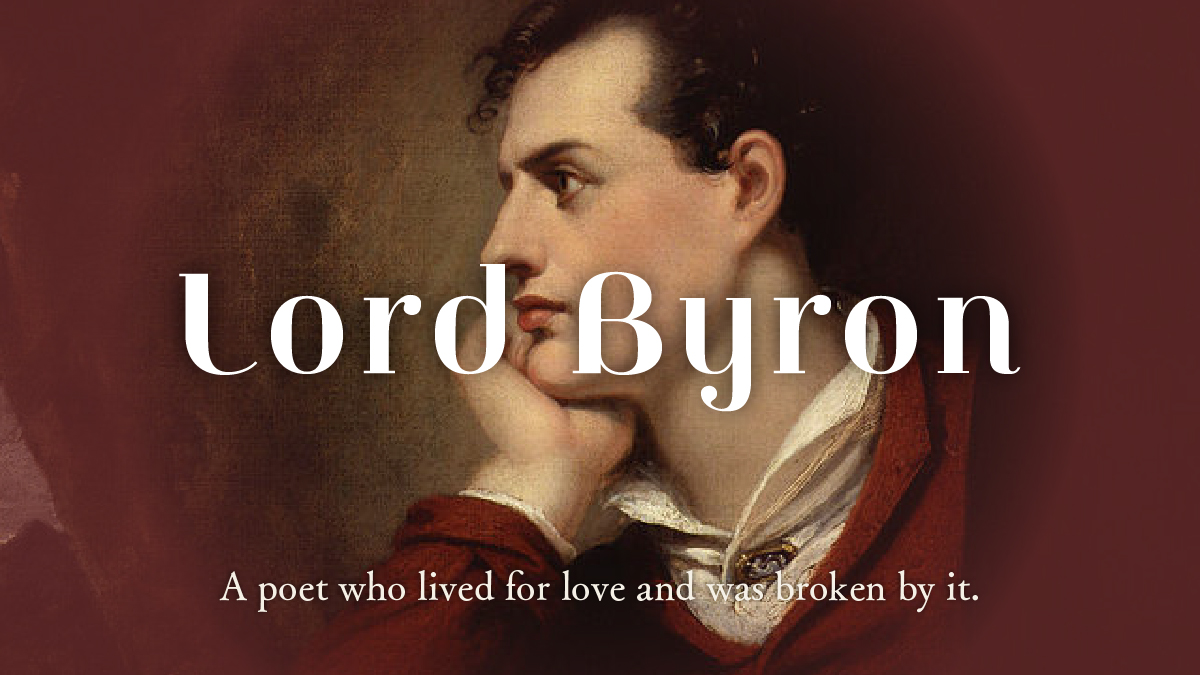


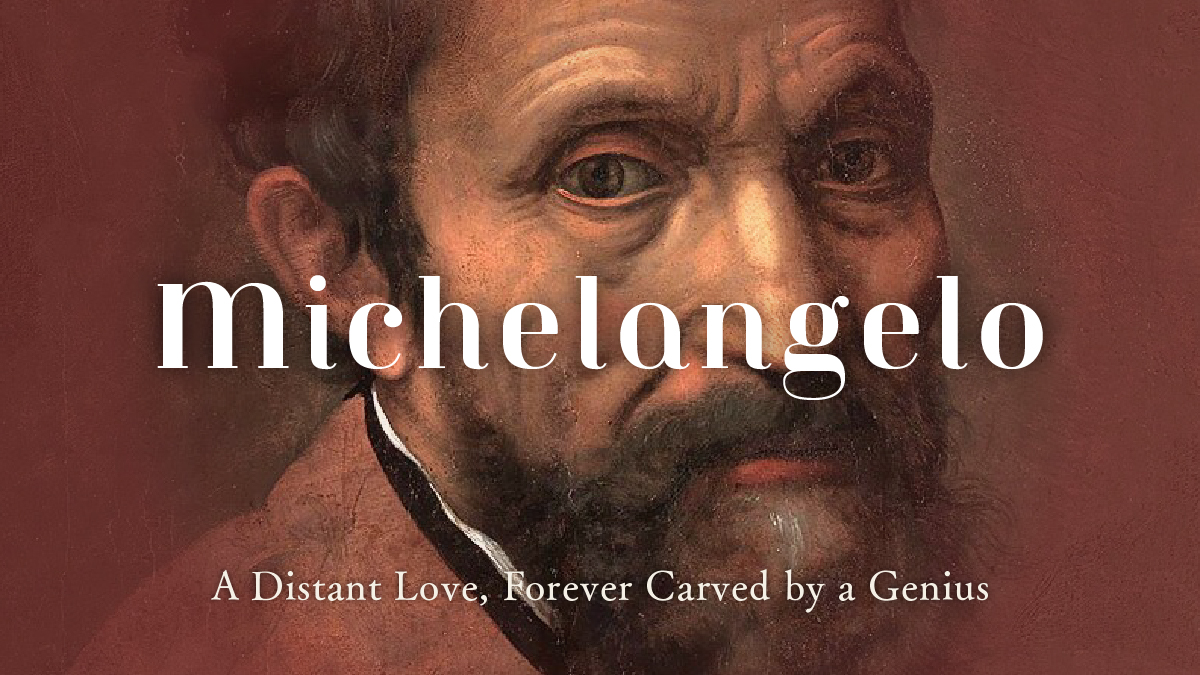
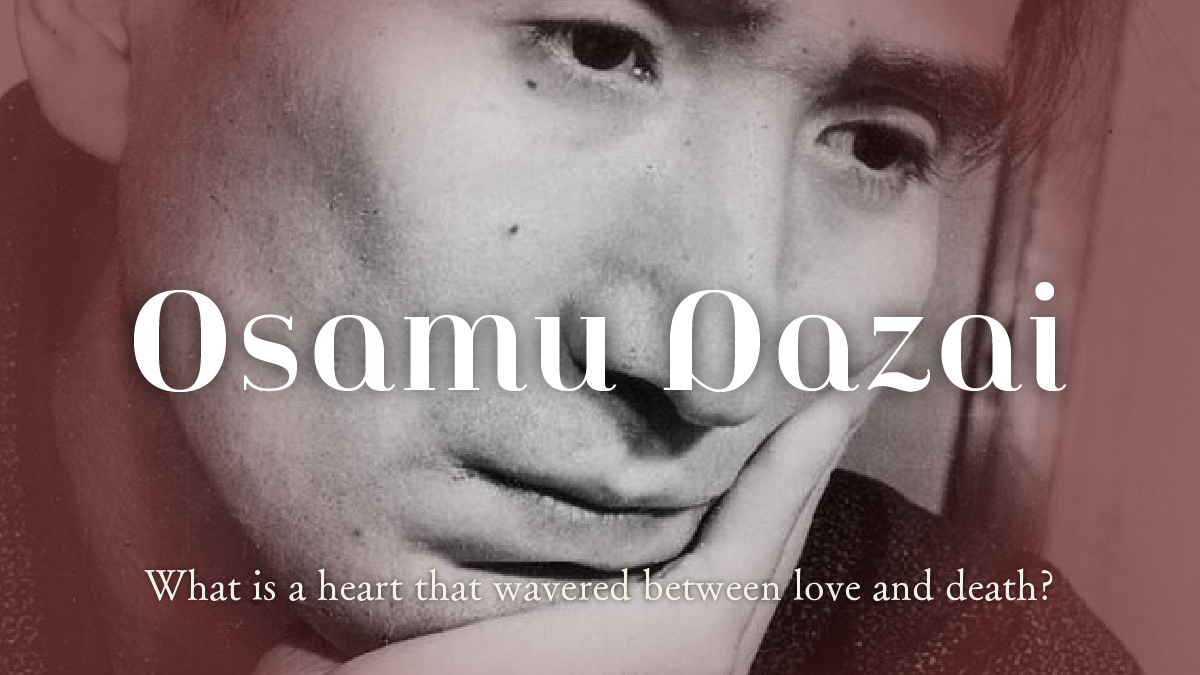


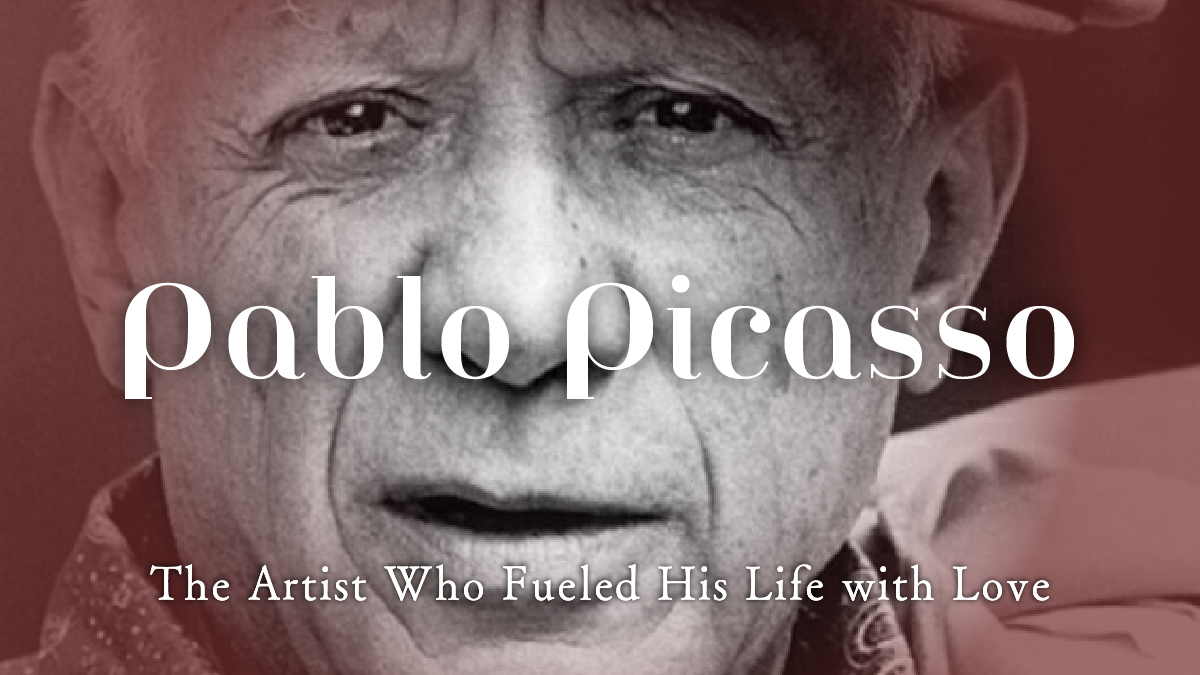
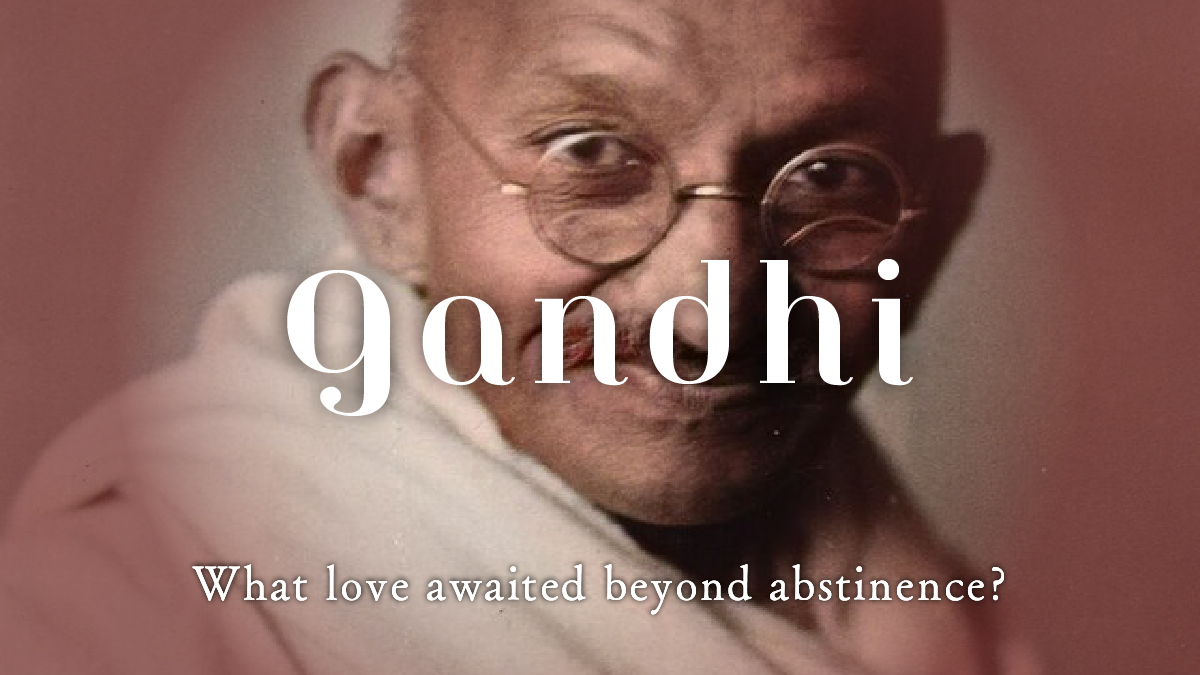

 English
English